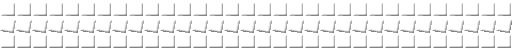 |
| 88円ライターじゃじゃモル |
| 「鈴木賞」受賞作 |
| ヤングレディ2名の芥川賞受賞作には大して感激のなかった私だが、若い人の作品はすべてダメ、なんて思ってはいない。高校時代、折に触れ接した生徒諸君の文章の中にもなかなかの非凡な才能を感じたことがある。 そろそろ私の文章に飽きてきた人もいると思うので、その中から特に感銘を受けた作品を紹介してみたい。 44回生と言えばH高で唯一3年間担任した学年だが、その中にK君(愛称金ちゃん)という生徒がいた。「真面目・堅物」を絵に描いたような人物なのだが、この彼の書く文章が何ともユニークだった。 とにかく駆使するボキャブラリーがただものではない。東京方面にもやたら脈絡関係不明の用語を使い散らかす自称文筆家がいるようであるが、金ちゃんは彼なりの筋道を貫いているように思われる。 下記の作品は学年便りにのったもので、秋の遠足の感想文であるが、彼の許可を得ずにここに転載する。著作権法的にはどうなんだろう? でも彼の人格ならよもや訴訟にはならないと思われるので・・・文章の中に出てくる「G君」とは、実は新生山岳部の部員名簿に名を連ね、後に信州大学に進んだあの彼である。 なお金ちゃんのその後であるが、彼は某国公立大学を小論文で受験するため、国語科のN先生に小論指導を受けていたのだが、N先生の添削が気に入らず、大ゲンカしてしまう。結果不合格。だが一浪後、私学のR館大学の文学部哲学科に進学することになった。今頃は一流の哲学者か、はたまた・・・ |
| 古都の表情と精神についての私見 |
| おちゃっぴいな少女の話し声がさながらトーンボエムのように私の耳に心安く感じられる空間をくぐりぬけて、嵯峨野らしい嵯峨野の風景を、一度舐めてしまったあめ玉のようにうるうるとした二つのまみにうつすのに、さほどの時間はかからなかった。ほっとため息をもらす間に、山林のうちに見透かされた念仏寺は、たちまち私の関心の外のものと化してしまった。そんな中で私の関心は、もっぱら嵯峨野におけるもっともラジカルであると思われる問題へ向けられていくのである。 私は嵯峨野のもつ清澄な表情、寂しげな表情、厳かな表情が大好きである。そんな瓦解の末の華族のような古都の表情が、私の冷たい心の中である温かい感情として具体化される、という中に私自身が幸福感を甘受できるからなのである。幼少のころから一貫してある私の好き嫌いというレベルの基本的な価値の形態にさらなる一貫性への道を与え、私を安心させるからである。 九歳の夏に、私は母に人体の図鑑を買い与えられた。私は目の前に余すところなく、プロレタリア詩のうねる叙情のようなはらわたを曝けだしているその本に当時ひどく執心していて、何週間とその本のページを繰り続けていたのだが、ある日をもってそうすることをぴたりとやめてしまった。それは、そうしている中で私の双眸にまさに焼きつけられんとするはらわたに、幼い私が無意識の拒絶感を抱いたからに違いない。 幼い頃のそうした拒絶感は、年を経てしだいに私のなかで倍加され、現在では無表情への嫌悪感と表情豊かなものへの親近感という二つの感情をつり合わせることで比較的おちついているにしても、やはり私のなかで戦慄の対象としての存在を誇示しつづけるのである。美しい女性の私が思いをよせる表情も、皮を一枚はいでしまうだけで、そこにはそんな表情のかけらもない筋肉の赤い糸の集まりと、ただ大きな眼球と、左右に白く不気味に輝く歯が長くいならぶばかりなのだ、という諦めが、昔も今も私の心をふさいでいる。 私はしみじみとして来し方をふりかえりつつ、古都の川の水面に一つうかんでいるボートに視線を送った。ボートには班員のH君とG君が乗っていて、小さくうずくまり伸びをするという単調な動作を繰り返していた。私が大きく手を振ると、彼らはそれにこたえてオールで大きくかいてボートを岸につけ、私を乗せてくれた。そうしてボートは吃水線から生まれてゆく糸たばをゆるめたような白い水のうねりを後にして岸から遠くなっていった。午後の光がうわぐすりのようになめらかにオールを握った私達のもとにながれると、私の目に友人の頬が漆器のようにつややかに見えた。私は目をそらした。次に目の前にタレントショップの屋根と道をゆく車のフロントガラスが輝いて見えた。うつりゆく古都の表情、そこに美しい女性の表情とどんな違った運命が与えられるというのか。 しかし私は自分が嵯峨野に足を踏み入れて感じた日本の精神の存在を否むことはなかった。古代現代の別なく、日本の精神はそれらの人々の生活単位なのであって、現代人にとって古代人の精神構造が全くの唐人の寝言であるなんてことはないはずである。 私達の行く道も帰る道も日本の精神につながっているならば、古都の表情は恒久的と言って過言でない。 |
| 雑文へ |
| メニューへ |