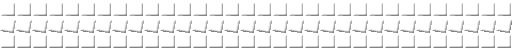 |
||
| 88円ライターじゃじゃモル | ||
| アテネ市民随想 | ||
| 体に6時間の時差を残してアテネオリンピックは終わってしまった。未だにその後遺症に苦しんでいるわけだが、これでジエンドにするのももったいないので、しばらくネタに使おうと思う。 新聞やネット上に様々な記事が載ったが、それらも参考にしつつ、ひと味違った角度からスポーツコメンテーターしてみたい。 | ||
| (1)嬉しい銀と悔しい銀 | ||
| 大会は柔道の金メダルラッシュから始まった。14階級中8個の金はお見事という他なく、中でも女子の5個は強いという一言だ。 野村の3連覇、谷の2連覇はとりわけ光り輝いている。内容的にもほとんど一本勝ちで文句のつけようがない。 この二人について「国民栄誉賞」が話題になった。高橋尚子がもらったとき、田村亮子がなぜもらえないかと言うことに関して、疑問の声が上がったことは周知の事実であろう。 ともに「Qちゃん」「ヤワラちゃん」というニックネームを持ち、国民的人気が高い。 しかも、高橋がオリンピック初出場なのに対して、田村は過去に銀2回の実績があった。不公平という非難は当然だろう。結局、「陸上競技女子では初の金メダル」が決め手になったと説明された。 今度はどうだろう。2度目の金で、さらに国民の注目度は高かった。だが、今回も見送られることになった。なぜだろう? 元々、「国民栄誉賞」なんてものは、一流選手の人気を現政権の人気にすり替えようとする策略にすぎない。橋本聖子や荻原健司の例を持ち出すまでもなく、一流選手は常に体制側に利用されやすい。一流選手といえど、引退後には生活の糧が必要だ。その弱味を巧みに利用して保守キャンペーンに結びつける汚いやり方である。谷選手にしても、後援会長は自民党の代議士であり、引退後はやはり政界から声がかかるに違いない。 当然「谷に栄誉賞をやれ。」という圧力は強かったと予想される。ところが、周りを見渡してみると、野村は谷を上回る3連覇、北島が金2個、野口みずきもマラソン連覇と、候補者がゴロゴロしている。誰かに出して誰かに出さないとまた「不公平」ブーイングが起きる。かと言って、これらすべてに出してしまうと、栄誉賞の有り難みが薄れてしまう。やむなく、受賞は見送られた。 「国民栄誉賞」をその名通り国民の総意に基づくものにするためには、選考委員を各界から選ぶとか、国民投票で決めるとかするべきだ。官邸のご都合主義だけで決めても誰が納得するものか。 金メダル8名のうちの7名にについては戦いぶりも見事であったが、しいてケチをつけるとすれば、女子78㎏超の塚田真紀選手、決勝戦は完全な負け試合だった。相手に投げられたとき、日本選手に辛い審判であれば即「一本」で終わっていただろう。「技あり」で命拾いし、どさくさにまぎれて抑え込んだ。もっとも相手の油断も実力のうちだから、金の値打ちに変わりはない。ただ塚田選手、あまり実力で勝ったと思いこまない方がいい。今後余程技と力を磨かないと連覇は難しいと言っておこう。 アテネのスタジオで、柔道のメダリスト全員がインタビューを受ける番組を見た。 ちょっと気になったのは、銀メダルの二人である。二人とも仏頂面で、嬉しさのかけらも感じられなかった。どうしてか? 金メダリスト達に囲まれている手前、自分たちは「銀」ということで気後れしていたのかも知れない。また、「銀」でも国民の期待はずれということで、喜ぶと叱られそうな気がしたのかも知れない。遙か昔のオリンピック、水泳の前畑秀子は、女性で初めて銀をとったのに「0.1秒差で銀とは何事か。」と責められ、そのことが次の大会で金をとる原動力になった。横澤選手も泉選手も、この悔しさをバネにすることで、北京での「金」を視界に入れていることだろう。 だが、それでも私は彼ら二人に言いたい。 「銀メダルでふてくされるとは何事か。」と。 外国選手を見ると、例え優勝候補が2位、3位に敗れても、晴れ晴れとした表情で表彰台に上がっているのが目につく。もちろん、内心に悔しさはあることだろう。だが、オリンピックで正々堂々と戦ったものとして、自分の成績に対して授与されるものは感謝の気持ちをもって受け取ることが大切だ。狙っても取れなかった競技者もおり、出場すらかなわなかった選手が世界には大勢いる。その代表として、オリンピックの権威に泥を塗るような態度は取ってほしくない。 横澤選手にしても、泉選手にしても、決勝戦は完敗であった。一か八かで仕掛けた技を返されて一本負けしている。すなわち銀メダルは実力通り。実力通りに下された評価を素直に受け取れないとはどういうことか。誤審で敗れても悪びれなかった篠原選手を見習いなさい。それでこそ北京で金を狙う資格があるというものだ。 また、日本選手に銅メダルがいないことも気になった。あの井上康生選手が代表的だが、1回負けたとたんに集中力を失って次の試合で力を出せないというのが日本選手の特徴でもある。これもメダルの権威を金にしかないと思いこむ重大な勘違い。それでこそ金が取れる、なんてふざけた事を言っていると、きっと世界の柔道界から返し技をくらうだろう。奢れるなんとかは久しからず、である。 一方、水泳のプールには爽やかな笑顔が輝いた。北島選手の強さは別格にしても、男子では200バタ山本選手、100背森田選手、400メドレーリレー、とメダルが続いた。この中で陰に隠れているが、敢闘賞を上げたいのはメドレーリレー、アンカー自由形の奥村幸大選手。第3泳者まではメダリスト揃いで強いのは当たり前だった。ところが自由形では他国との力の差は歴然としている。にもかかわらず、奥村選手は見事リードを守りきった。日本記録でもある自己ベスト。まさにリレーの醍醐味である。 女子では200バタ中西選手、200背中村選手、この二人は「狙って取った銅」だった。そして圧巻は800自由形の柴田亜衣選手。「無欲の金」の典型だろう。まさにシンデレラ・ガール。でもカボチャの馬車は消えなかった。 「国技」として「金」を期待される柔道と、あくまでチャレンジャーである水泳との差、と言ってしまえばそれまでだ。だが、観衆の心にいつまでも残る爽やかな笑顔が 「見るスポーツ」としてのオリンピックにはよく似合う。(このシリーズ続く) |
||
| (2)野口はいかにして金に届いたか | ||
| HPの掲示板をご覧になった方ならご存知だろうが、私は野口の金メダルと、ラドクリフの途中棄権を「「半分くらい」当てた。このレースに関する限り、あのインチキ占い師H木K子よりも遙かに冴えていたんではないかと自認している。 現地の「賭け率」では、日本の3選手のうち、土佐が一番上位だったという。これはおそらく自己最高記録で単純に比較したためだろう。正確な順位は覚えていないが、この土佐でさえ賭け率の3位以内には入っていない。現地での下馬評では、日本選手の連覇はまず不可能な線だった。欧州での開催と言うことで、予測も欧州贔屓に傾く傾向はあるにしても・・・・ 私ですら、ラドクリフ本命説を完全に否定できないくらい、彼女の下馬評は圧倒的だった。2時間15分台の世界記録は、高橋尚子やヌデレバと比べても、抜きん出ており、順当に実力を発揮できればまさに敵無しの感があった。 だが、彼女には弱点もあると私は見ていた。まず、暑さ。彼女はその名前からするとゲルマン系のようだが、夏場の酷暑マラソンでゲルマン系が勝った例を私はほとんど知らない。白人でも、イタリア・スペイン・ポルトガルなどラテン系は暑さに大変強く、オリンピックでも実績を残している。また、アングロサクソンも、イギリスのジョーンズなどメダルを取ったこともあるのだが。 また、彼女の走り方は上下動が大変大きく、力で持っていくタイプ。この走法は、アップダウンの激しい今回のようなコースではリスクが大きい。すなわち、無駄なエネルギーを消費して筋肉や内臓に疲労を蓄積してしまいやすいのだ。案の定、35㎞での彼女のリタイアは、まさに疲労困憊の姿だった。もちろん、完走しようと思えばできたとは思うが、金メダルが絶望になった時点でレースは終わり。銅メダルが精一杯のレース展開では、モチベーションが維持できなかったのだろう。 それにしても、暑さに強いはずのアフリカ勢がバタバタ脱落していくさま(特に男子が象徴的だったが)は、黒人が必ずしも酷暑レースに強いわけではないことを示してくれた。ケニアやエチオピアの長距離選手は大部分が高地民族で、それほど暑さに慣れているわけではないのだ。 日本選手の話に戻るが、3名の中では、私は野口が頭一つ抜けていると見ていた。その根拠は・・・昨年のパリ世界選手権では、ヌデレバについで野口が2位に入り、今回補欠の千葉が3位、坂本が4位だった。だが、坂本はその後急成長し、選考レースの大阪国際では圧倒的な強さを見せ、千葉らを抑えて優勝した。だから、パリの結果がそのまま反映すると思っていたわけではない。 根拠の第1は、スピード、とりわけスパート力である。野口は「ハーフマラソンの女王」と呼ばれるくらい、より短い距離で実績がある。小柄にもかかわらずストライドを伸ばすその走法には他の2選手よりも切れ味がある。外国勢との争いになったとき、集団から抜け出すためには一瞬のスパートの切れ味、これが必要不可欠で、中途半端なスパートでは却ってライバルにとって絶好の刺激になり、切り返しを食らってしまう。 その点では、坂本直子にも期待するものがあった。大阪国際の30㎞で見せたロングスパートは5㎞15分台という見事なものだった。だが、アテネでは消極的なレース運びをしたのがアダになった。レース直前のインタビューが中継で流されたが、野口が「チャンスがあれば自分から仕掛けたい。」と答えたのに対し、坂本は「誰かが出ればそれについていきたい。」と答えている。この時点で、すでに坂本は気持ち負けしている。キャリアの浅い坂本こそ、捨て身で仕掛ける覚悟でなければ並み居る強豪を倒せるわけがない。野口の「チャレンジャー精神」、これが大きく勝負を分けるキーポイントになったと考えられる。 根拠の第2、それは「シード」の有利さである。野口はもっとも早く代表に決定し、このアテネに向けて万全の準備ができた。それに対し、他の2選手は、選考レースに勝つことがまず先決で、アテネの準備はそれが終わって疲れが取れてから、ということになり、結果的に1年近い準備期間の差ができた。これは決して無視できない。 かつて有森裕子が2大会連続でメダルを取ったが、彼女のアドバンテージは、世界選手権や北海道マラソンで他の選手よりもいち早く代表の座を確定し、すべてをオリンピックに本番に注ぎ込めたことである。シドニーでこの位置にあったのは、市橋有里であったが、彼女は余りに「純粋培養」すぎて、修羅場に適さなかった。その後どうなったのか、最近は消息も聞かないが・・・ そして根拠の3番目は、野口選手は「苦労人」であること。有森にしても、高橋にしても、「エリートコース」ですんなりと一流選手になれたわけではない。二人とも、最初は、「スポーツ推薦」なんてとんでもなく、自らコーチの門をたたいて入部したような無名選手である。その後、所属チームの廃部があったり、コーチについて退社したりと、紆余曲折を乗り越えながら力をつけた。マラソンに関しては、このような「雑草」選手が強いというのが日本の趨勢である。(男子では瀬古は「純粋培養」だが、中山は「雑草」) 野口は三重県の出身であるが、家庭は貧しく、兄と姉は中卒で就職した。野口だけが陸上競技を続けたいと、兄と姉の懇願もあって高校に進学した。高校時代は無名、だが彼女も実業団に入ってからこつこつと力をつけてきた「這い上がり」組だ。この「ハングリー」度が、日本選手では一番と見た。 以上の3つが私が野口を推した根拠だが、レースが終わってから飛び込んできた情報(インターネットで読んだ)があった。それは「シューズ」の選択に関してである。 この女子3選手のマラソンシューズは、アシックスのある職人さん(名前は覚えていない)がすべて作っている。この職人さんが大会前にアテネ入りしてコースを下見したとき、気付いたことがあった。それは、アテネのマラソンコースには、大理石の石畳が結構多いと言うことである。走らない人にはわからないことだが、アスファルトよりもコンクリートや石畳の道は、硬くて脚に負担がかかる。そこで、その職人さんがピンときたのは、こういう硬い道には通常の「ウレタン底」よりも、「スポンジ底」の方が合うのではないか、ということだった。そこで両者を試作してみて、3選手にはいてもらって選ばせると、土佐と坂本は、「やっぱりはき慣れたウレタン底の方がいい。」と言ったのに対し、野口だけが素直にアドバイスを受け入れて「スポンジ底」に変えたのだという。 実際に靴が勝負を左右したのかどうか、それは分からない。だが、ここで特筆すべきは、野口の専門家に対する信頼の念である。日本の女子選手の場合、いいコーチに巡り会い、そのコーチを信頼して練習に取り組んだ場合にいい結果が出ている。有森と高橋がともに小出門下であることは周知の事実だが、かつて世界選手権のマラソンを制した浅利純子や鈴木博美のケースも、コーチとの二人三脚なしでは考えられなかった。すなわち善悪は別にして、日本女子マラソン選手はまだ競技者として完全に自立しておらず、コーチのアドバイスに忠実に従った場合によい結果が出ているのである。 野口は自我を捨て、コーチや専門家の意見を素直に吸収し、そして金に届いた。あの、常識的には早すぎると見える25㎞スパートもコーチのアドバイス通りだった。もちろん、誰もがそれを成功させる力を持っているわけではないが。 野口選手に関して、スポーツコメンテーターとしても活躍している例の乙武さんが、こんなコラムを書いていた。いわく、「野口は高橋の幻影に追いかけられて走っていた。」だが、私はこれには異論がある。いったん、用意ドンでピストルが鳴ったら、そんな雑念など忍び込んでくる余地などないのだ。無心に走り、無心に予定の作戦を実行した。それが見事成功したまでだ。 だが、ちょっと冷や冷やした場面があった。競技場に入ったとき、ヌデレバがすぐそこまで迫っているのに、野口選手、呑気に観客席に向かって手を振っていた。あれだけ大勢の応援団がアテネに押しかけておきながら、なぜ誰も後続との差を教えてやらないのだ。野口のチーム関係者も一体何をしていたのだろう。私なら、 「うしろー、ヌデレバ100mきてるよーーーー!!!」と叫んでやるが。次の北京では関係者に一考をお願いしたい。 それにしても、一度も画面に映らなかったわが友人ザビエル氏(坂本直子3年間担任)にとってはどんなアテネであったのだろう。今度会ったら聞いてみたい。 今日(9月18日)テレビでインタビューに答えていたが、もちろん次の北京の連覇は彼女の視野に入っているだろう。坂本直子はもちろん雪辱に燃えて来るだろうし、1万㍍では国内無敵の福士加代子あたりも次は参戦してくるかも知れない。だが。彼女が持ち前の素直さとチャレンジ精神を失わない限り、北京もまた彼女を軸にした争いになるのは間違いない。 容貌的には高橋尚子ほどの華はなく、地味な彼女ではあるけれでも、偉大なランナーとして世界に認められるようになってほしい。おそまきながら、アテネで初めて彼女のファンになったじゃじゃモルなのである。 (このシリーズ続く) |
||
| (3)愛ちゃんの「サー!」 | ||
| メダルも入賞も逃したのに注目されまくった選手と言えば、文句なしに卓球の福原愛ちゃんである。 それにしても、依怙贔屓という言葉は彼女のためにあるのではないかと言わんばかりの報道だった。同じ女子卓球には、梅村礼選手と藤沼亜衣選手も出場していて、愛ちゃんと同じくベスト16まで進んでいる、にもかかわらず、私の知る限り、この両選手は一切テレビ画面には映らなかった。(すみません、うちはBS契約してないもんで・・・)両選手の関係者は非常に不愉快な思いをしたに違いない。そんなブーイングさえ吹き飛ばしてしまうくらい彼女の国民的人気は凄いのか、と改めて驚かされた。 何しろ、一時は「暗い」スポーツとしてどんどん競技人口が減り、中学校や高校の公式団体戦でも、それまでの「4人制」を、「2人制」に変えざるを得ないくらい落ち込んでいたのである。それを現在の人気に高めたのは、漫画「稲中卓球部」と愛ちゃんだと言われているくらいなのだ。そんな彼女の魅力とは何なのだろうか。 彼女の称号として、「天才卓球少女」という言葉が使われる。だが、これは間違いだと私は思う。卓球という競技に「天賦の才能」なんてあるわけがない。彼女に与えられるべき称号は「天才」ではなく「英才」である。 3歳から徹底的に鍛えられれば、あれくらいの選手はどんどん出現するはずである。それだけの環境がなかなか実現しないだけなのだ。 福原選手、体は可哀想なくらい小さい。しかもぽっちゃりした体脂肪型の体型。基礎体力だって到底抜群とは思えない。反射神経や動体視力にしても、イチローにはほど遠いだろうし、それさえもほとんどは訓練の産物である。 しいて言えば、彼女の性格は勝負師向きかも知れない。幼い頃、よくテレビ画面に登場して、タレントなど、素人の大人と対戦していた。そのとき、負けるとすぐ涙ぐんでいたのを皆さんの多くは覚えておられるに違いない。個人競技や囲碁将棋をやらない人には、ピンと来ないかも知れないが、「泣き虫」は一流になるための条件なのである。 囲碁や将棋の一流選手に共通するエピソードとして、自分より強い人に負けたとき、悔しがって涙をこぼし、何度も何度も向かっていった、というのがある。「負けず嫌い」それが人一倍強くて、泣かずにいられない。そして、泣くのが嫌なばかりに、人一倍努力して勝つことを目指す。それが「壁を超える」飛躍的向上につながるのである。 ああ、じゃじゃモルが何をやっても一流になれなかったのはまさにそれだったのでは・・・私は人に負けて悔しかった、ということがない。負けた理由を「運が悪かった。」とか、「ちょっと練習が足らなかった。」とか、「体調が悪かった。」と、すぐに合理化してしまい、「次こそは」と燃えることがない。マラソンだって、自己記録こそ目標にせよ、他人に対抗意識を持ったことなど一度もなかった。 オリンピックに先立った世界選手権ではベスト8に入ったし、彼女は「超一流」が手の届くところに来ていると思って間違いないだろう。だが、ここから先が大変なのである。ここで足踏みし、そして消えていった選手の何と多いことか。いい例が、同じ「愛ちゃん」。テニスの杉山愛選手である。ダブルスプレーヤーとしてはウィンブルドンを制した彼女も、シングルではメジャー大会で目立った実績がない。外国選手に比べて、やはり体格・体力的に一回り劣るのがその理由と見る。 いくらテニスほどパワーを要求されない卓球でも、愛ちゃんの前途は決して容易ではない。それが、韓国選手に敗れたオリンピックの準々決勝に垣間見えた。 相手はカットマンであった。カットといのは、守りに重点を置いた技術であり、とにかく相手に攻めさせてミスを誘う。そして、相手の油断を突いて反撃し、攪乱するのだ。カットマンを倒す一般的戦術はこうだ。とにかく、ドライブ(トップスピンをかける攻撃法)を相手のコート奥深く打ち込み、相手を台から下がらせる。機を見てドロップショットをネット際に落とし、相手の返球が浮いたところをスマッシュで決める。 愛ちゃん、最初はこの戦術を忠実に守り、順調に見えた。ところが、だんだんとミスが多くなってきた。ドライブにしても、スマッシュにしても、パワーが劣る分、「決定力」に欠ける。相手は彼女の打球に慣れてくるが、彼女はだんだんスタミナと集中力を切らせて競り負けるパターンだ。高校生になり、もう体格の向上は望めない彼女にとって、この壁は意外に大きいと見る。 攻撃型を相手にする場合も問題がある。彼女はオリンピックの半年前、バックハンド側のラバーを変えた。それまで「イボ高」と呼ばれる変則回転するラバーを使っていたのを、「表ソフト」に変えた。「表ソフト」はスピードを重視するラバーである。すなわち、相手のミスを誘うバックハンドを「スピードで圧倒する」タイプに変えたのだ。リーチが短く、両サイドに振られたとき不利な彼女は、台にぴったりつく、いわゆる「前陣攻守型」にならざるをえない。体格で上回る中国選手などは、どんどん強いドライブを打ち込んでくるだろう。それを前陣でさばきつつ、どこかで「反撃」しないといけない。パワー負けしない突破口が果たして彼女にあるのか?泣いただけでは済まない「変身」を将来の彼女に期待したいものだ。 ところで、愛ちゃんのもう一つの魅力は、あのインタビューの面白さである。幼い頃から卓球漬けの毎日で、普通の少女とは生育歴がまるで違う彼女は、ときとしてエイリアンのような返答をして報道陣を煙に巻く。 その報道陣がやたらに繰り返した質問がこれである。 「ポイントを上げたときに出すあの声は、一体何と言っているんですか?」 それに対して愛ちゃんは、 「恥ずかしいから答えません。」と言っていた。 代わりに私が答えてあげよう。卓球プレーヤー、私は関西の選手しか知らないが、ポイントを取ったとき、 「ヨッシャー!」と叫ぶ人が多い。これがある人では 「ヨッサー!」になる。ここから「ヨッ」がとれたのが 「サー!」である。 ちなみに、関西では「サー!」はサーブを出す前に自分自身に気合いを入れるときに使うことが多いのだが、国際ルールではサーブの前の声は禁止されているのかも知れず、それを出している選手はあまり見たことがない。 じゃじゃモル、イヤに卓球に詳しいじゃないか、といぶかる方もおられるだろう。三流といえど、一応元実業団選手です。(このシリーズ続く) |
||
| (4)アヌシュと室伏~場外の逆転 | ||
| ドーピングの歴史は意外に古い。私の記憶の範囲では、初期のドーピングは「興奮剤」から始まったようである。競走馬に抹茶を食わせるとよく走るというが、人間にもカフェインを大量に注射すると、運動中枢が冴えまくって好成績につながるらしい。だが、そんなものは現在からするとまだ可愛いものであった。 やがて、「筋肉増強剤」の時代に入る。男性ホルモンないしはその構造的類似物質を継続的に使用することによって、通常のトレーニングと食事では得られないような強靱な筋肉が手に入る。 かつて共産圏に東ドイツという国があった。人口は日本の3分の1程度でありながら、陸上や水泳などの競技で次々とトップアスリートを輩出していた。金メダル数ではアメリカと旧ソ連に次ぐ実績を誇っていたが、そのトレーニングメソッドは当然ながら赤いベールに包まれていた。 その「秘密」がドーピングであったことが確定的になったのは、ベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが統一されてからだ。アテネの成績を見るがいい。東西合併でメダル数が増えないといけないはずなのに、現状は日本をさえ下回っている。特に、旧東独のお家芸であった陸上・水泳での凋落は目を覆うばかりだ。 ドーピング漬けは何も共産圏に限った話ではない。ベン・ジョンソンは金メダルを剥奪されたが、それに代わって金に繰り上がったカール・ルイスにも疑惑がくすぶっている。 女子100mで10秒59という驚異的な世界新を出したフローレンス・ジョイナーは30歳の若さで心臓病のためこの世を去った。死人に口なしと言うが、その原因がドーピングにあると疑うのはごく自然なことである。 要するに、バレなければ最高の栄誉と富が手に入る可能性があり、バレればすべてを失う。ドーピングは宝くじ以上に魅力的なギャンブルと言っても過言ではない。 貧しい旧共産圏のハンガリー。田舎の一教師に過ぎなかったアヌシュは、野心家のコーチのもとで、ドーピングに手を染める。みるみる伸びる成績。たちまち世界の舞台へと彼は躍り出る。もっとも、彼に全く素質がなければ、そんなことは実現しなかっただろうが。五輪の金メダルにも手が届きそうになったとき、彼はもう違反行為から手を引くことはできなくなっていた。そんな彼を最初に告発したのは、「ご近所の住民」だったと言う。健全なるかな、ハンガリー国民、その何割かは「妬み」であったとしても・・・ 提訴するやしないや、未だに悪あがきを繰り返してはいるが、彼のハンガリアン・ドリームは崩れ去った。ギャンブルの結末としてはよくあることである。 そして栄光の座に駆け上がったのはわが室伏選手。「アジアの鉄人」と呼ばれた名選手を父に、やり投げ選手であったルーマニア人の母をもつ彼は、あまりにカッコよすぎる。言ったら悪いが、同じ日本人としての親近感が湧かないのは私だけだろうか。 年齢(29歳)に似合わぬ落ち着きといい、ただ者じゃない。スポーツ選手で終わるとは思えぬ。将来は俳優か、政治家か・・・ ドーピングとは無縁(なはず!)の彼は、「サラブレッドの血」と、「卓越したコーチング環境」を武器に、これからも黄金時代を築くだろう。五輪直後のTOTOスーパー陸上でも、好記録で圧勝し、まさに「真実の王者」となった。ただ、プロスポーツ選手と違って、待遇面が恵まれないのは気の毒に思える。その点については後述しよう。 ドーピングに話題は戻るが、科学技術とりわけ医療技術の進歩は、ドーピングにも多様化をもたらした。造血ホルモン「エリスロポエチン」を用いた血液ドーピングは見破ることが可能だが、自分自身の赤血球を保存しておいて、競技前に注射する手口は、容易に見破ることができない。 そして最近まことしやかに囁かれているのが「遺伝子ドーピング」である。優秀な競技者の遺伝子を、ベクターと呼ばれる「運び屋」ウィルスに乗せて細胞に送り込む。「誰でもピカソ」じゃないが、「誰でも室伏」が実現しかねない。「完全犯罪」の企みとのイタチごっこは永遠に続くのか・・・ ここで原点に立ち返って考えてみると、アンチ・ドーピングの基本は「選手の生命や健康を守る」ためであって、「競技の公平性」はその次である。莫大な報奨金を出す国と、中途半端なアマチュアリズムが横行する国とでは、元々環境条件に差がありすぎる。 いっそのこと、陸上競技などは、世界的プロ組織を作って、各国の一流選手をすべてプロとして独立させてはどうだろうか。4年に1回しかチャンスがないからギャンブルに走る選手も出るが、継続的に賞金試合があれば、「バレたら永久追放」になる賭けに走る選手は少なくなると思うがどうだろうか。ドーピング検査も精密かつ継続的にやればよい。言わば車検を毎月やるがごとく・・・ 一市民ランナーとして申し上げれば、「上には上がある」。ドーピングもアンチドーピングも「雲の上の話」には違いない。 次のレース、抹茶でも食って走ってみようか・・・(このシリーズ続く) |
||
| (5)貧打に泣く | ||
| どちらも予選リーグ・決勝トーナメントと立て続けにオーストラリアに負けて銅メダル。野球とソフトボールはあたかも一卵性双生児のような結果になった。 だが、その原因は異なるようだ。今回はその辺りを分析してみたい。 まず野球。こいつは、「選手選び」から問題があったと言わざるを得ない。 100%プロの「ドリームチーム」を作ろうという構想。これには賛否両論があるだろう。賛成者の言い分は、「金メダルを取ることによって、国民とりわけこれからプロを目指す野球少年達に夢を与える。」というのがメインであろう。反対者の言い分は、「アマチュアを排除することによって、ノンプロや大学野球選手の夢を奪う。」そんなところではないかと思われる。私もどっちが正しいかと言われれば判断に迷う。だが確かに言えることは、ドリームチームを選んだ以上、どこやらの元校長の決まり文句ではないが、「勝たねばならぬ」重い十字架が選手やスタッフに背負わされるということである。 私が問題にしたいのは、プロアマ議論ではなくて、プロから選んだ場合の選手構成のことである。各チーム2名ずつ、計24名の選手団。登録人数の上限が果たしてピッタリの24名であるのかどうか、それについては残念ながら私は情報を持たない。もしそうだとするなら、あまりに日本球界に都合がよくできすぎていると思うが。もし25名以上だとするなら、当然アマからも選ばれていたはずだから、その点に関しては疑わないことにしよう。 さて、選手の全メンバーを眺め渡してみて、まず気付くことがある。それは投手が24名中11名と異常に多いことである。(高校野球は、確か17名のベンチ入りで、投手は普通3名程度である。)これは、勝つためにそうしたのではなく、「ペナントレースへの影響を最小限にあるため、各球団の戦力ダウンを均等にする」ことが理由であるのは見え見えだ。投手の内訳を見てみると、セ・リーグが各球団1名ずつ選ばれているのに対して、パ・リーグはオリックスと日ハムは2名とも野手で投手を出していないのに対し、千葉ロッテは2名とも投手である。セが「公平」を原則にしたのに対し、パは「チーム事情」を優先したようである。 結局、試合数から見ても日程からも見ても明らかに投手が多すぎて野手が足りない布陣で日本は本番に臨んだ。そして、豪州投手陣に抑え込まれた。 過去の五輪の戦歴を見ても、キューバが最大の敵であることは間違いなかった。だが、一番手の敵に目を奪われ、第二、第三のライバルに足元をすくわれるということはよくあることではないか。今回の日本がまさにそれだった。 豪州の先発投手はアメリカの3A在籍選手で、情報が入らなかったのはやむを得ないと言われるかも知れない。だが、豪州のスタッフは随分前から日本のプロ野球に偵察隊を送り込んでいたようだ。ならば日本も豪州のラインナップが決定した時点で、3A偵察隊を派遣してもよかったのではないか。1試合だけでも見ると見ないでは大差である。 それよりも致命的なミスは、早くから豪州チームに加わるということがわかっていた阪神のウィリアムス、彼に対する対策を全くぬかっていたという点だ。最近ウィリアムスの成績はあまり芳しくなかったので、ナメていたのだろうか。ウィリアムスを得意にする打者を1名でも選手に加えるか、もしくはその選手からのアドバイスをきっちり受けておくべきであった。長島という人物は元々そういった緻密な点を欠く指導者だが、中畑もそれに準じた欠陥構造の持ち主と言わざるを得ない。 リードを許した終盤、マウンドに上がったウィリアムスに対して、日本は左打者をそのまま打席に送るしかなかった。唯一の右の代打であるはずの日ハム・金子は現地での練習で足を負傷して出場できない状態であったという。ウィリアムスと同僚の藤本がぶざまに三振する様子は惨めを通り越していた。 総合力では明らかに上と思われる日本が負けたのは、どう見ても油断による取りこぼし。アマの夢を奪ったマイナス面を加算すると、銅メダルという成績は「ふがいない。」と言わざるを得ない。北京で二の舞を繰り返すようだとタダじゃ済まない。 次にソフトボールである。宇津木監督という人物を私はよく知らない。だが、敢えて言わせてもらうなら、「一点集中型」で、広く状況を見て判断するという資質には欠けている人に思える。その理由を以下に述べる。 シドニーの決勝は、本当に惜しい試合であった。あの試合のとき、私は特殊なシチュエーションにいたので、はっきり思い出すことができる。4年前の冬、マラソンが済んだらニュージーランドに行くつもりだった私は、大阪の谷町九丁目にあるアトラストレック社を説明会のために訪ね、その帰りラジオ中継を聴きながら梅田まで歩いていた。息詰まるような投手戦、だが日本に1点が入り、終盤に入るが、本塁打で同点にされて迎えた最終回。アメリカ選手のレフトフライを左翼手が転んで落球。惜しくも銀メダルに終わったのだった。彼女には悪いが、ラジオで聴いたこのシーンで思い出した場面がある。巨人V9の年、ペナントレース終盤までリードしていた阪神が、これに勝てば優勝は決定的と思われる直接対決で、センター池田選手が何でもない飛球をやはりズッコケて長打にして負けた試合である。あれで流れが変わり、最終戦の巨人逆転優勝につながったのだった。 あの試合で、宇津木監督が思ったことは、「守備さえ強化すればアメリカには勝てる。」ではなかったか。だが、彼女は見落としていた。日本は次からはマークされた存在になることを。 確かに日本の投手力はすばらしかった。エースの上野、控えの高山、ともに安定感は抜群。だが、やはり勝つためには点を取らなければならない。 ここ一番での貧打に泣いた日本。その原因を分析してみると、どうも次のように思われる。アメリカや豪州の投手の日本人打者に対する攻め方はパターン化していた。とにかくまず直球で押す。非力な日本人選手は大抵力負けするか、大振りして振り遅れるかしてくれる。とりわけ大振りの典型は4・5番の斉藤・宇津木両選手であった。あれだけ長く持って振り回せば、確かに弱小チームの投手からは長打が奪える。ところが、アメリカなどのエースに対しても、同じ振りで勝負をしようとして墓穴を掘っていた。そして、ファウルで粘ってくると見るや、一転チェンジアップ等の変化球で打ち取る。決まったパターンなのに日本は打ち崩せなかった。その理由はパワー不足もあるが、それを補う工夫がなかった所にあると私は見た。 一つは、どの打者もすべて全打席・全投球「直球狙い」であったこと。これは「ゲームの理論」をちょっとかじればわかることだが、投手が例えば5球中4球を速球、1球を変化球で勝負してくるとする。最も打てる確率の高い選択は、実はすべて速球狙いではなくて、5球に1球は変化球を狙うことなのだ。もっともこれは純粋に確率論的な計算であって、実際にはいろいろな心理的駆け引き等の問題があって難しいが、宇津木ジャパンのように、馬鹿正直に速球ばかり狙う戦略は、不利であることは疑いない。「狙い球を切り替える」練習を普段からやっていたかどうか、おそらくその答は「否」だろう。敵にマークされたチームが勝とうと思えば、そのような高度な戦略がないと勝てない。「策に溺れる」ことを嫌って「横綱相撲」を取ろうとする。これは日本のスポーツ指導者がしばしば犯す誤りである。 また、強打で力負けするなら、もっとバントでかき回す作戦もあってよかった。この大会、日本のセーフティバントが成功する場面をほとんど見なかった。成功率の問題ではなくて、試技数がはっきり少ないのである。打率が1割台で、投手圧倒的有利のソフトボールにおいては、あらゆる工夫が必要だというのに・・・例えバントが失敗に終わっても、それによって内野手の守備を前方に引きつけ、内野手間を抜くヒットを出やすくする効果もあるのだ。 投手もまた馬鹿正直だった。日本の投手は、一人目の打者から、パーフェクトゲームを狙うようなつもりで、ぶっ飛ばしていた。だから、終盤やタイブレークに入ってから球威が落ちて打ち込まれる場面が目立った。それに対してアメリカや豪州は、ランナーが出るまでは楽に投げておいて、スコアリングポジションにランナーが進むや、一転全力で投げ込んでタイムリーを許さないしたたかさが目立った。 結果的に銅メダルは「実力通り」、以上でも以下でもないと私は見る。だから、野球と違って「よくやった。」と讃えてあげたい。でも、「金を取りたいならそれではだめですよ。」という一言を添えて・・・(このシリーズ続く) |
||
| (6)リレーの醍醐味 | ||
| 「リレー」にはある種の憧れとコンプレックスがある。もはや自ら持って走る境遇ではなくなった今も、バトンのあの冷たい感触と、それをつなぐ瞬間の熱い想いはハートをくすぐってやまない。 小学校高学年になると、校区の中学校の体育祭を見に行くのが慣例になっていた。単に見るだけではない。その中のある競技に「参加する」ことが半ば義務づけられていたからである。私の場合、その参加方法はもっぱら「応援」であったが・・・ 「部落対抗リレー」なんて、とんでもない名前をつけたものだ。さすがに「部落」はその後「地区」に変わったような記憶もあるが・・・要するに、町名(私の場合、押部谷町)の次にくる「大字」毎に選手を選んで競うリレーである。学年毎に1名の選手枠だが、「小学生枠」というのもあった。私の場合の地区名は「福住市住」。(私の家は「福住」でなく、「西盛」で、市営住宅ではないが、近隣がそうだからしょうがない。)その小学生枠に私が選ばれる可能性はなかった。なぜなら、近所に同学年のS君という自分より速い子がいたからである。 「ヨーイ、ドン」でスタートが切られる。最初は小学生の女子。ついで男子にバトンが渡る。同学年の女子に飛び抜けて速い子がいて、「福住市住」はトップで来る。S君がバトンを引き継いで走り出すが、その直後、他の地区の選手が後方から襲いかかり、あっという間にS君を追い越す。バックストレートに入ると、もっと速い奴が来てトップを奪う・・・わがS君は顔をゆがめ、必死に追いすがるが、ジリジリと差が開いて後方へ・・・こうしてデッドヒートは中3男子のアンカーまで続くわけである。 S君には悪いが、私はうわべは悔しがりながらも、心の中では密かに快感を抱いていた記憶がある。 「あのS君が負けた。」自分は走らせてもらえず、万一走ったとしてももっと惨めな結果になるのはわかっていても、「上には上がいる」ことを確認し、自分の鈍足を妙に納得してしまうのだ。 私は中2くらいからようやく体力が伸び始め、体格もS君を追い越して、おそらく走るのも速くなっていた。だがその頃、すでに体育祭には「地区対抗リレー」という種目は消えていた。なぜ廃止されたかの理由はさだかでない。 リレーの醍醐味である「抜きつ抜かれつ」のデッドヒートを、世界の超一流選手達がやってくれるとしたら、これほどの見ものはない。とりわけ好きなのはマイルリレーだ。最後の直線に入るまで優劣の判然としない400リレーと違って、マイルリレーは2走のバックストレートからはオープンコースで、順位の上げ下げが手に取るように見える。それも最高のスピード感を伴って・・・まるで格闘技のようなスリルが味わえる。 アテネで日本男子陸上陣は4×100と、4×400、両方で4位入賞という快挙を成し遂げてくれた。メダルにこそ届かなかったとはいえ、これは凄いことだという認識をわれわれは持たねばならないだろう。何しろ、個人では100も400も誰一人準決勝にすら進めなかったのである。 1×4>4 この不等式を実現可能にしたものは何か?ロスのない絶妙のバトンパスもさることながら、それ以上に選手個々のモチベーションが最高に高揚した結果と見る。すなわち「団体競技」として各自の気持ちが一つになったのだ。 余興のような運動会はともかく、「リレーで勝つ」、とりわけ「アンカーでゴールテープを切る」瞬間はもはや私には訪れそうにない。だが、少年時代に夢見ながら実現しなかった華麗なゴボウ抜きを、これからもTV中継を見るたびに夢想し続けるに違いない。 と書いて完結しようと思ったら、この私が「ゴボウ抜き」を達成した経験がただ1回あったのを思い出した。その自慢話を書いてしまおう。 それはもちろん400やマイルリレーではない。「駅伝」である。S高に転勤して4年目だったと思う。その前の年から、「S高激走クラブ」は、平荘湖駅伝大会に出場していた。この駅伝は、加古川にある平荘湖というダム湖の周回コースで行われるものである。1週4.8㎞のコースだから、どの区間も4.8㎞とわかりやすいのだが、1部から5部まであって、1部から3部が実業団、4部が女子、5部が高齢者とちょっとこの辺がややこしいのだが・・・ 私達は弱体チームとて、3部への出場であった。1区から6区まであって、私の担当区間は2区。これがたまたま幸運をもたらしたのであった。まず1部がスタートし、その5分後に2部から5部が一斉に出る。この日、わがチームはメンバーが足りず、1区を担当したのはS高教員ではなく、誰かの友人F君であった。F君、年齢は20代で若いものの、普段トレーニングらしいトレーニングをしておらず、いきなり苦戦であった。彼が中継地点にようやくたどり着いたときには、タイムは21分以上かかっており、順位は全部含めても100位を超えていたのではなかろうか。 たすきを受け取った私はいきなりハイペースで飛び出した。短い距離だから、ペース配分も何もあったものではない。一人旅だと、なかなかそう最初からペースには乗れないものだが、この日はうまい具合に、前に一杯先行ランナーがいた。しかも抜くには手頃なオジさんやオバさんばかり・・・ 一人、また一人とぶっこ抜くのは気持ちがよく、私はたちまちにしてリズムに乗った。ちゃんと抜いた人数も数えていた。抜けばまた次の目標が見える。そいつを目指して突っ走ればどんどん差が縮まり、並んでかわせばまた次のカモが手頃な距離に見えている。結局、私が3区に引き継ぐまでに抜いた人数は70人。タイムは16分52秒。陸上部顧問をしていたM先生に、「十分高校駅伝の選手で使えるよ。」とお褒めの言葉をいただいた。 これにはおまけがついた。翌日職員室が何やら騒がしい。神戸新聞を持ってN先生が近づいてくる。 「鈴木さん、区間賞や、区間賞!」 確かによくよく見ると、3部の2区の所に私の区間1位が載っているでないか。特別タイムが速かったわけではない。たまたま同じ区間に速い人がいなかっただけなのだが、それでも一生涯で二度ともらえるかどうかわからないものだから、やはり嬉しかった。そんなこととは露知らないものだから、閉会式にも出ず帰ったのだが、表彰状は後日郵便で届いた。今でもリビングに飾っている。 この駅伝、その何年後かにも「3部団体10位入賞」の快挙をわがチームは成し遂げる。いや何、アンカーにS高OBで、インター杯に出たF君に走ってもらっただけなのだが・・・それでも入賞ギリギリの順位で飛び込むなんて、平荘湖はゲンのいい大会である。 周りの人たちがみんな走ることをやめてしまい、現在駅伝には出たくとも出ることができない。今一番出たいのは「富士登山駅伝」。一番高い所の登りをやってみたい、なんて大それた願望だろうか・・・(このシリーズ完) |
||
| 雑文書きへ | ||
| メニューへ | ||
| |