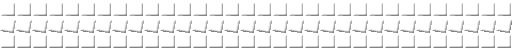 |
| 88�~���C�^�[���Ⴖ�Ⴢ�� |
| �s���O�|���O�����L |
| ��P�́@���w���� |
| �@�ʂɑ̈狳�t�ƊԈ����킯�ł͂Ȃ��̂����A�u�^���͉�������Ă��܂������H�v�Ɛu����邱�Ƃ�����B�����������ꍇ�A�����ē�����Ƃ���u�싅�v�Ƃ������͂Ȃ��B�����A���܂�傫�Ȑ��Ō����Ȃ����R�����͂���B �@�������̊���ŁA����l�C�����������싅�ł͂��邪�A�u�N�ɂł��V�ׂ�ȒP�ȃX�|�[�c�v�Ƃ����C���[�W�̗��ɁA���́u��ω����[������X�|�[�c�v�Ƃ������Ԃ�����B�����g�A���̉��܂ł͂ƂĂ��ɂ߂Ă͂��炸�A�����킩��Ȃ����Ƃ��炯�B�ƂĂ�����Ȃ����A�u�o���҂ł��B�v�Ƌ����Č����Ȃ��Ƃ����̂������ȏ����B �@�싅�ɂ��Ă͑��̏ꏊ�ł����낢�돑���Ă��邪�A�_�u�邱�Ƃ����m�Ŏ��̑싅�j���Ђ��Ƃ��Ă݂����B �@���P�̂P�w�����A���㕔�ŗ������ڂ�đ��H�Ɋׂ��Ă������͑싅���̖���������B���������́A�c�Ȃ��݂̗F�B�����܂��ܑ싅���ɂ��āA�u���Ȃ����B�v�ƗU���Ă��ꂽ���Ƃł���B�������A���̗F�B�ƗV�тł���Ă��āu�ʔ������v�Ɗ��������Ƃ����R�ł���B�Z�p���������Ȃ��A�������P�b�g�ɓ��ĂĕԂ������̃s���|���ł������B���肪����Ă���Ă��邱�Ƃ��m�炸�A�u���߂Ăɂ��Ă͉��������B�v�Ȃ�Ďv���Ă����B �@�����A���̊Â��v���͂����܂��ł��ӂ��ꂽ�B�̈�قɒu���ꂽ�싅��͂S�䂵���Ȃ��B���R�㋉�����D��ŁA�P�N���͂����ς�f�U��ƕ⋭�^���B�Q���ڂő������ؓ��ɁB�����A���x�͂�߂Ȃ������̂́A�u�����オ�Ȃ��B�v�Ƃ����v���ƁA�싅���̕��͋C��`�[�����[�g�Ƃ̑����������Ă������炾�낤�B �@���Z�̕��ł́A�u�P�N���̂����͋���ł����Ă��炦�Ȃ��B�v�Ȃ�Ęb�������Ă����B�����A�����̑싅���͌ږ�͖��O�����A��y�̓�������r�I��邭�A���R�ȕ��͋C�������B��b�̗͂��ł��Ă��炸�A�g���[�j���O�ŃA�b�v�A�b�v���鎄�ɂ��A�������݂�������A�u�lj��ł������v�Ȃ�Ă����C�W�����Ȃ��A���̗̑͂͏������オ��A����̃��x���ɒǂ����Ă������B���㕔�ł͐L�тȂ��������������̗͂��A�����ŐL�т��͓̂��M���ׂ����Ƃ��낤�B �@�ċx�݂͂��܂�Ȃ��ʔ��������B���K�ɖO�����l�����́A�ږ�̐搶�ɂ��肢�ɍs���B �@�u�搶�A�v�[���̌��݂��āI�v �@�����A�����̓v�[�����ł�������ŁA�܂����j���͂Ȃ������B���̕��́u���j�͌����₷�B�v�Ƃ������R�Ńv�[���ɂ͓���Ȃ��B�v�[���͂܂��ɑ싅���̑ݐȂ̂ł������B����܂ő��p���Ȃ��łP�T�������j���Ȃ��������́A�����܂��Q�T���ȏ�j����悤�ɂȂ�B�R�[�`�Ȃ��̎��ȗ��ł���B�w�j�Ȃ�ĂQ�N���̉ċx�ݖ����́u�Z�����j���v�ŗD�����Ă��܂�����E�E�E �@�ږ₪���炸�A�Z�p�w���͐�y����̒��`�̂݁B�P�N��ɐV�l��Ŏs�̃x�X�g�W�����P�U�����܂ōs������y�����āA�����ς炻�̐�y�̃}�l�����邭�炢���ւ̎R�������B���R�݂�Ȏ��ȗ��̌ł܂�A����Ӗ����h�����̏W�c�ł������B���̊w�N�͍ŏ��������ĂV���ł������̂����A��ԏ�肢�z���r���Ŏ��߂Ă��܂��A�U���ɂȂ����B���C�o���͂T���Ƃ������ƂɂȂ�B���̒��ŁA����U���Ă��ꂽ�ނ����͈�Ԏキ�A���͂����ɔނ�ǂ������Ă��܂����B���Ƃ̂S���Ƃ͎��͔����A���[�O�����邽�тɏ��ʂ��ς��B�l��͂Q���A�c�̐���V���O���͂S�������o���Ȃ��B���Ƃ����Ƃ��Ɨ��K�ɂ͔M�����������B �@�����������AH���Z�ɐi�w���đ싅���ɂ���Ƃ�����y���w���ɗ��Ă��ꂽ���Ƃ�����B���̂Ƃ�����������ŁA��������ł������Z�p�w���̗v�ɂ��Ă��邱�Ƃ�����B����͑f�U��̎��A�u���P�b�g�p�O�p�`�ɐU��B�v�Ƃ������Ƃ��B�悭�A�����^���őf�U�肵�Ă���l�����邪�A����ł͎���ɑΉ��ł��Ȃ��B����̎��̕ԋ��̓t�H�A�ɗ��邩�o�b�N�ɂ��邩�킩��Ȃ����炾�B�t�H�A��U������A���P�b�g�����ɍ~�낵�Ă���A���̂ǂ���ɂ��Ή��ł���B���ꂾ���͎������g�̏�B�ɂ��A�싅�����̎w���ɂ��傢�ɖ𗧂������A���ł��𗧂��Ă���B �@�����āA�u�f�U��̑���B�v����͖싅��e�j�X�ȂǑ��̃X�|�[�c�ɂ����ʂ��邱�ƂƂ��āA��ɔO���ɂ���B�X�E�B���O�̗͋����A���萫�͂܂��ɑf�U����ǂꂾ����������ɂ������Ă���B�N�ɐ������P�b�g�������Ȃ��Ȃ��Ă��A�ŋ��̃^�C�~���O������Ȃ��̂́A�̑f�U�����������ł߂����炾�B�{��w�Z�̐��k�ł���A���̊�{�͓������Ǝv���Ă���B������ŋ��O�̑f�U��͌������Ȃ��B �@�����g�̑싅�X�^�C���B�p�`�y���z���_�[�ŁA�h���C�u�^�B���̃h���C�u�A�������K�������ʃ}�X�^�[�����̂����A�ŋ��_�𗎂Ƃ��Ă����邽�߁A����̕ԋ����ƑΉ��ł����A��]�͂悭�����邪�A�~�X�����������B���݂ł͂��̑ł����͔r�˂���Ă���B�ŋ��̍ō��_�ł�����u�g�b�v�ł��v�����݂̎嗬�ł���B�o�b�N�n���h�͊������ӂŁA�o�b�N�X�}�b�V�����ł���B�����A���ꂪ�p���ăA�_�ɂȂ��āA���������Ƀo�b�N�Ŏ�낤�Ƃ�����ɓI�ȃQ�[���^�тɂȂ邱�Ƃ������A�����A���Ɍ�����̏����͗ǂ��Ȃ������B�T�[�u�̓J�b�g�m�[�J�b�g�ɉ����āA���E����]�A�߁A�����O�A�u���Ⴊ�ݍ��݁v�܂Ŋ܂߂Ă��̎�ސ��ɂ͐�ΓI���M�����������A����܂��T�[�u�ɗ��낤�Ƃ��Ď��ł���P�[�X�����X�B���̕ӂ肪�싅�̓���Ȃ̂ł���B���ǑI��Ƃ��Ă͎O�����O���A������ł��P�̂�����t�ŁA������u�Q���{�[�C�v�ŏI����Ă��܂����B �@���Q�̉č��h�ɂ͋ꂢ�v���o������B���h�ƌ����Ă�������u�Z�����h�v�ŁA�w�Z�ɐQ���܂肵�Ȃ�����̂ł���B���̕��́A���ړx�������A�e���d���܂ł��ׂĂ���Ă����̂����A�싅���͂��ׂĎ��������ł�邵���Ȃ��B�ږ���w�Z�ɂ͂��Ă���؎�`���Ă���Ȃ��B���͂�͉��Ɨ��Ȏ��̃o�[�i�[���g���č�����B���́u�������v���ďo���̂����A��闿���A��闿���A���ׂĕs�]�ŁA�قƂ�ǂ��c�тɂȂ����B�Q��̂��A�z�c���ѕz���Ȃ��A�̈�ق̃t���A�ɂ���Q�B�ł��Ė��ꂽ���̂ł͂Ȃ������B������������o���Ă��Ȃ����A�悭�����c�������̂��B �@���R�ɂȂ��āA�싅���͓~�̎�����}�����BM�Ƃ����������A�ȑO��������ږ�Ȃ��Ŋ������Ă���싅���Ɍ�����������Ă���A���т��ш��͂������Ă��Ă����̂����A�Ƃ��Ƃ��싅���͑̈�ق�ǂ��o����A�����ɉ������܂�Ă��܂����̂��B������肩�A�u�V�P�N������������ȁB�v�Ƃ����ʒB�B�u�p���ʍ��v�ł���B�N�����o���A���k���狳�t�ɗ����ς��Ă��A�u�����X�|�[�c�͕s���S�v�ȂǂƂ������_���������Ď��B�𔗊Q�������̋��������͋����C�ɂȂ�Ȃ��B �@�K���A���B�̑��ƌ�A�����싅���͕������A�x�e�����ږ�̎w���őS�����܂ōs�����Ƃ����b�����BM�����̈��I�݂͐������Ȃ������̂ł���B�u�ߓx�̎��O���͑̂Ɉ����B�v�Ƃ���������펯�ƂȂ���鍡�A�����ɂ��悭�P�K�����Ȃ��싅�́A���ɏ����ɂ̓I�X�X���ł���B �@�����āA���w�Z���ƁB���Z�ł��܂���肽���A�Ƃ����v���Ƀu���[�L���������̂́E�E�E�����͂܂������ŁB�@�@ |
| ��Q�́@�A����� |
| �@�����č��Z���w�B�܂��싅������肽���Ƃ����C�����́A���̓t�B�t�e�B�t�B�t�e�B�A���̐S�͗h��Ă����B �@����Ƃ����̂��A���w�ƈ���Ēʊw���Ԃ������A���������ƋA��x���Ȃ�B�w�ƂƗ����ł��鎩�M���Ȃ��������炾�����B���Ƃ��Ɗ挒�ȑ̎��ł͂Ȃ��A��ꂪ���܂�₷���A�����s���Ɏア�B���̏�A�S�̕��e���� �u��w�ŁA��ɘQ�l�͋����ʁB�v�Ɛ鍐����Ă����̂��B �@�����玩������싅���̃h�A��@�����Ƃ͂��Ȃ������B������Ɓu�l�q���v�ł���B�Ђ���Ƃ��Č��������犩�U���Ă��邩�ȁH��������l���Ă݂悤���ȁH�ȂǂƁE�E�E �@�Ƃ��낪�A���������Ă����̂́A���Ƃ����낤�Ƀo�X�P�b�g���ƌ������������B���̐g�����������Ĕ��f�����炵���B�ǂ�����S���o���̂Ȃ��X�|�[�c�ŁA�ƂĂ�����Ȃ������S�҂���n�߂�C�͂Ȃ������B �@�����A���������Ă����̂��A�o���[���Ƃ��e�j�X����������A���̐S�͓����������m��Ȃ��B���Ƀo���[�́A�f�l�Ȃ����D���ŁA���w�Z�̋��Z���ł͊����肵�Ă����B����H���̃o���[���́A���̂R�N���A���ŗD�����ăC���^�[�n�C�ɏo��̉����𐬂��������B�����Ђ���Ƃ��Ă��̈���ɁH���H���M�����[�ɂȂ������āH�R�N�ł��̃o���[���̃��M�����[�Ɠ����N���X�ɂȂ����̂����A�̈�̎��ƂŔނ͎��Ƃǂ������ǂ������̗͗ʂ������̂ł���B �@���̂����A���F�ő싅���ɓ��������z�炪���X�Ǝ��߂Ă����B���ł��A�����͖�x���A���j���܂Ŋۂ��Ɨ��K�ŁA�����鎞�ԂȂǂȂ��̂��Ƃ����B���̐S�͌��܂����B�싅�Ɛi�H�͗��V���ɂ������Ȃ��B�@�^�ږ�̔M���w���ŁA���̐��N��A�싅���͌��ł���ʂ𑈂����x���ɂȂ邪�A���̈���ɂȂ�Ȃ��������Ƃ������͂��Ȃ��B���F�A��e��ǂ��҂͈�e���������ł���B �@���Z�̂R�N�ԁA�قƂ�ǃ��P�b�g�͈���Ȃ������B��x�A���F�ƗV�тő싅��ɍs���A���̒��̑f�l�ɁA���̓Q�[���ŕ����Ă��܂����B�u�����̃��P�b�g����Ȃ�����B�v�Ƃ����̂͌�����ɂ͂ł��Ȃ������B������������P�b�g�Ńv���[���Ă���̂��B���̎����Đ��܂ꂽ�����コ�ɂ��̌���Y�܂���邱�ƂɂȂ�B �@�싅�͂�����߂����̂́A�܂����̐S�ɂ͉����������Ԃ��Ă����B�l���Ă݂���A�싅�ō��܂��A����ō��܂��A����Ɠ��݂Ƃǂ܂����X�|�[�c�ł���B����𓊂��o���ĉʂ����ĉ�������̂��B�X�|�[�c�Ŕт�H������͂Ȃ����A���͂���ł����\�X�|�[�c�D���l�Ԃ̂���ł���B�Ⴆ�����ǂ�Ȏd���ɏA�����Ƃ��A�X�|�[�c�͑��������B �@��w���w�オ�܂���̓]�@�������B���Z�Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�f�J����w�̑̈�فB���̒n���ɂ���싅���̗��K������͌��w�ɍs�����B�j���̕��������悭���K���Ă����B�������ꎕ�������Ȃ��قǍ������x���ł͂Ȃ��B �@���̎茳�ɂ������u�̈��v�̃p���t���b�g���L���Ă݂��B���̒��ɑ싅���̃y�[�W������A���U���b�Z�[�W�ƂƂ��ɋL����Ă����̂́A�u����@�����S�C�O�O�O�v�B���̋��z�Ɏ��͑���ۂB�܂��A���o�C�g���Ȃ��A�e�̎d���肾���̎��ɂ͂������z�������B��Ȃ��b�����A���̋��z������̈��n�ɓ���邱�Ƃ����B �@�������āA���͕����n�T�[�N���w���ƂȂ����B���{���ł̑̈���Z�̎��Ԃ��炢�����^���̃`�����X�͂Ȃ������B�������A�K���������̂́A�ʊw�Œ��������]�Ԃɏ���Ă������ƂƁA�e�H�̂��߂S�N�ԑS���̏d�̕ϓ����Ȃ������i�T�X�s�j���Ƃ��A���^�{���b�N�nj�Q�ɂȂ邱�Ƃ�j�~���Ă��ꂽ���Ƃ��B���Z�̃s�[�N���ɔ�ׂđ̗͎͂���������̂́A�u���팠�v�͎���Ȃ������B �@�����ĂЂ��ȂP���̊w���́A�ӊw�Z�Ƃ�����Q���w�Z�̋��t�ɂȂ�B�����ő҂��Ă����̂́A���������o���F�̎Љ�l�����������B�i�Â��j |
| ��R�́@���u�I�[������ |
| �@1983�N�t�A���͋����Ƃ��Ėӊw�Z�ɕ��C�����B�����͕��ʍZ�Ɠ����悤�ȕ�����������A���́u�㎋�싅���v�̌ږ�ɏA�C����B �@���́A�Ⴂ���t�̑唼�������ł���悤�ɁA���̎w���ɑł����B����܂ł����Ƃ�����{�Z�p��������Ă��Ȃ����S�ғ��R�̐��k�������A�f�U�肩��̃X�^�[�g�������B�����g�A�䗬�ł���Ă����g�ł���Ȃ���A���S�Ҏw���ɂ͓V���̍˔\���������悤���B�ނ�͂߂��߂��r���グ�A�u�싅�v�̌`���ł��Ă������B �@�U���ɏ��߂Ă̋ߋE�ӊw�Z�싅���A�{�Z�ōs����Ƃ������ƂŁA���͓��ꍞ��ł����B�����ōD���т��グ�Đ����ɏ�肽���B �@�����A�����^�ɂ͌������ꂽ�B�c�̐�̓��C�o���Ɩڂ��ꂽ�w�Z�ɐɔs���A�l��ɖ]�݂����������B���ƂP������Ώ�Ɏ肪�͂��Ƃ����厖�Ȏ����A���̓x���`�őҋ@���Ă����B���͔����̏����ł���A�ē̃A�h�o�C�X�����s�ɒ�������B�Ƃ��낪�A�����{�Z�̂s�Ƃ����̈狳�t���猾��ꂽ�̂́A �@�u���̎����A�����R����B�v �@��ÍZ������A�N�����R�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�����A�R���ɂȂ�x���`�R�[�`�͂ł��Ȃ��B���̎����Ɍ����ẮA�x���`�ɂ������Ăق��������B������A�ʂ̐E���ɑ���ɐR�������肢�����̂����A���ꂪ���̑̈狳�t�ɂ͋C�ɓ���Ȃ������悤���B �@�u�����A���͂��ɐR������ƌ������͂���B�v �@������Ɖ����ⓚ�ɂȂ����B���ǁA��ւ͔F�߂�ꂽ���A�������n�܂��ĊԂ��Ȃ��A����������d�b�̌Ăяo�������������B�d�b�ɏo��ƁA����͎��̖����炾�����B �@�u���A�Z�����A��������]�쌌�œ|��āA����Ă�˂�B�v �@�u���H�ق�܂��B�v �@���͕��S��ԁB���͂�R�[�`�������Ȃ������B�������ʂ��҂����ɕa�@�ɋ삯���˂Ȃ�Ȃ������B �@���̍�����̈�ȂƂ��a瀂��ڗ��悤�ɂȂ����B���������̃y�[�X�ŕ��������肽�����ƁA�^�����͂��ׂđ̈�Ȃ̊NJ����ł���Ƃ���s�Ƃ̊ԂŖ��C���N�����B���K��̃~�[�e�B���O�ŁA���̌��������ƂƔ��̂��Ƃ��킴�Ɛ��k�����Ɍ����s�B���k�����̎�O�A�䖝�͂��Ă������A�X�g���X�̂��܂���X�E�E�E �@�Q�N�ځA���q�����̈�l���ߋE���l��𐧂����B�������A�������������A���͂�͂�c�̐���Ƃ肽���Ǝv�����B�����A���q�����͏������Ă������̂́A�j�q�����͂s�̕��Ɍ����ꂵ�Ă��܂��A���̎w���ɏ]�����Ƃ��Ȃ������B�c�̐�͒j�������Ȃ̂ŁA���q�����ł͏��ĂȂ��B�Ǐ������B �@�R�N�ځA���͎㎋�싅���ږ����]�����A�ږ₩��͂��ꂽ�B�j�q�������������̋C�������킩�����悤�ŁA����������ӂ��Ă����B�����܂��A�����ɕ��A����Ƃ�����ɂ��������A���́u�S�ӑ싅���v�i��̏��]�����싅�j�̌ږ�����Ȃ���A�����猩��邱�ƂɂȂ����B���̔N�ɏ��߂Ēc�̐킪�ߋE���𐧂����͔̂���ƌ������Ȃ��B �@���̊ԁA�ږ�Ƃ��Ă͘r��U�邦�Ȃ������������A�ӊw�Z�̑��Ɛ��𒆐S�ɂ��������ƒc�`�[���u���u�I�[���v�ɉ�����āA�T�P��ł͂��邪�A�V�J�n�́u�_�ˎs�g��҃Z���^�[�v�ŗ��K�ɎQ�������Ă�����Ă����B �@�����ł͂��낢��Ȑg��҂̕��Ɨ��K�����ɂ����B���r�Ƃ����悪�Ȃ��A���P�b�g���^�I���ł�����ăv���[���Ă���l�B�����g����Ⴢŕs���R�ŁA�قƂ�Ǐ㔼�g�����̓����őłl�B�g��҂�����ƌ����ĉ���������Ȃ��Ă���ƁA���K�Q�[���ł��R�e���p���ɂ��ꂽ�B�ǂ�ȑ���ł��낤�ƁA���т����R�[�X��˂��A��������ł��Ȃ��Ə��ĂȂ��B���ꂪ��Ԋw���Ƃł���B �@������ɂ��o���B�_�ˎs���ƒc�Z�����[�O�B�����łR�`�S�`�[���̒c�̃��[�O����s���A��ʂɂȂ�Όܕ��ɏオ���B��x�ܕ��ɏオ�������Ƃ����邪�A�����ł͗͂̍������������Ċ��s�A���Z�������������B�B �@�����g�̍v���x�ƌ����E�E�E���̓V���O���X�ł͂قƂ�Ǐ��ĂȂ������B���̍�����u�C�{�����o�[�v�Ȃ���̂�����āA������g���Ă���I��Ɠ����邱�Ƃ������������Ƃ����R�̈�����A��͂莄���g�́u����コ�v���낤�B �@�������M���ׂ��́A�_�u���X�Ŕ����������|�I�����ł���B�_�ˎs���ӊw�Z�̋����ł���l�搶�Ƒg�y�A�͂قƂ�ǖ��G�������B�����T�[�u��h���C�u�Ń`�����X�{�[��������A�l�搶���X�}�b�V���Ō��߂�A���̏����p�^�[�����o���オ���Ă����B�V���O���X�ƈ���āA�_�u���X�͌���ɑł��߁A�P���ł��Ă��玟�܂łɁu�l����]�T�v������B���̂��Ƃ��A���ɂ͌����Ă���悤���B��ɍd���e�j�X��������Ƃ����_�u���X�̕�������ς苭�������̂͋��R�ł͂Ȃ����낤�B �@���̑싅�j��ŁA���̍�����ԋ��������̂͊ԈႢ�Ȃ��B�o�b�N�n���h�ł��X�}�b�V�����r�V�r�V���߂Ă������A�h���C�u�̈З͂����������B�����A�����قǁA�u�����͑싅�Ƃ������Z�ɂ͌����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�v�Ɗ����������̂��������B �@�싅�ł́A�ǂ�ȃX�[�p�[�v���[���}�~�X�������P�_�ł���B���̐��i�ł́A�P�{�X�[�p�[�v���[�����߂�ƕ����オ���Ă��܂��A���̌�}�~�X���J��Ԃ����肷��B��ɕ���S�ŔS�苭���v���[����l�̕������̋��Z�ɂ͌����Ă���Ǝv���B �@�T�N�ځA�̈�ȂŌ�����U����Ă����s���l���ٓ��ł��Ȃ��Ȃ����B����Ŏ����̓V���ɂȂ����Ǝv�����̂����̊ԁA�͂̂��镔�����������Ƃ��Ă��܂��A���ǐl�ޓ�ɋ������ƂɂȂ����B�����g�����ꂪ�ӊw�Z�Ō�̔N�ɂȂ�A�ږ�Ƃ��Ă͕s���S�R�Ă̂܂܋��邱�ƂɂȂ����B �@���Z�]�����܂����Ƃ��A�������̍Z�����玄�������n���ꂽ�̂́u�T�b�J�[���ږ�v�B���āA�싅�̕��͂ǂ��Ȃ�̂��H�i�Â��j�@ |
| ��S�́@����Α싅���ږ� |
| �@�T�b�J�[���ږ⎞��̂��Ƃɂ��Ă͂ǂ����ŏ��������A����̖{��ł͂Ȃ��B�㖡�̈����v�����c���Ď��͈�N�ŃT�b�J�[������߁A�O��̑싅���ږ�ɏA�C�����B�����A����ł������菇�������ɍs���قǐ��̒��Â��͂Ȃ��B �@�ꏏ�Ɍږ��g�ރx�e�����s�搶�̗v���ŁA���͒j�q�̕���S�������̂����A���ꂪ�ǂ����ԈႢ�̌������������m��Ȃ��B�ӊw�Z������������������A���͕������̎w���Ɋւ��ẮA���q�����Ƃ̕����������悢�B�j�q�����́A������Ƙr���グ�Ă���ƁA���ȗ��Ɋׂ��Čږ�̌������Ƃ��Ȃ��Ȃ�X��������B�����Ōږ�͂��̎v���オ������ӂ��čĂю����̎w�����ɏ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��낤���A���͂����Ȃ����Ƃ��A���i��u����ɂ����B�v�Ǝw����������Ă��܂���_������B���ɁA���w�Z���ォ�炠����x���т��グ�Ă��镔���̏ꍇ�A�ږ�̃A�h�o�C�X�Ȃ�Ă܂�ő���ɂ��Ȃ��B���̂Ƃ��̂R�N������тQ�N���������������B���̓_�A���q�͐^���ɃA�h�o�C�X������Ă����̂Ŏw�����₷���B �@�R�N���́A��N�̐V�l��Œc�̌��x�X�g�W�Ɏc���Ă���A���̕��V��ɂȂ��Ă����B���̂悤�ɂ����Ȃ�ږ�ɂȂ����V�ċ��t�Ȃǃn�i���瑊��ɂ��Ȃ������B�܂�����ł��A�Ǝ��͋C����蒼�����B���̔N���w�����P�N�������͌������Ƃ��悤�Ɉ�Ă悤�E�E�E �@���̗\�z�ʂ�A�R�N���̃G�[�X�Q���͖��S����L�єY�݁A�v���悤�Ɏ��т͏オ��Ȃ������B�����̂͒c�̂���������Q��핉���A�l��V���O������ʂɐi�߂Ȃ������B�����A�R�N���̂R�Ԏ�ƂQ�N���̑g�_�u���X�������ǂ������킯�������i�݁A������юO�{�����ւ̏o�ꌠ���B �@���̗����͂��܂��ܖL���ŊJ����A��l��A��Ĕ��܂肪���ň��������B�ǂ����̑��������͖Y�ꂽ���A���Ŕd�A���������������A�L���̐e�ނɎԂŌ}���ɗ��Ă��炢�A�����Ŕ��߂Ă���������Ƃ����������v���o�����B���傤�ǂ��̐e�ނ͂������̍Œ��ŁA�������T���������ɂ͂�点��ꂸ�A������l�łT�P���炢�������A�����r���ؓ��ɂɁE�E�E �@���̂Q�N�����������ӋC�ȓz���������A�r���őޕ����Ă��܂��A���Ƃɂ͏����̂Q�N���ƂP�N�����c�����B�Q�N���̎叫�������z�ȋC�̗����Ȃ��j���������A�P�N���͎��̂�����ݒʂ�ږ�Ƃ̐���ȊW���m�����Ă����Ă��ꂽ�B���h���a�C�\�X�y������ꂽ�B���́A�����{�[�b�Ɨ��K�����Ă��邾���̎w���͌������B�����ƃ��P�b�g�������A�����ڐ��ɗ����ď��߂Čږ₽�蓾��Ǝv���Ă���B���̍��h�̍g����ŁA���͒j�q�̎叫�ɏ������B������Ƃ͊����グ�����ȁB�܂��A���s�ɂ�����炸�A�����Ƃ̋����͂ǂ�ǂ�k�܂��čs���̂������Ă����B��ɁA���̕��������͑��̂P���Ŗ���g���i���̕�Z�j��|���Ƃ��������𐬂������Ă��ꂽ�B���̂Ƃ��A�g���ł͔s��̐ӔC���Ƃ��ĕ�����R�[�`���ۊ��葍��������قǂ̃V���b�N�����ƌ���������B�܂��A���̊w�N�͑��ƌ���n�a��ɏ��҂��Ă���A���̏�ł����������𗬂����Ă��B�{���ɐl�Ȃ������p�Ȏq�����������悤�Ɋ�����B �@���̂P�N������́A���͏��q�����Ɏ���o���n�߂��B������Ƒ҂āA�ςȈӖ�����Ȃ��B�Z�p�I�ɂ͂�����x�O�a�ɒB���Ă���j�q�ƈႢ�A���q�͂�����Ǝ�����Ă��Ƃ߂��߂������Ȃ�B�j�q�̉��ŗ��K���Ă��鏗�q������ƁA�ǂ����Ă��Z�p�w������ꂽ���Ȃ�B���̒��ł͕��������Ă����l�q�ƍ��ӂɂȂ�A���N�O�c�ōs���Ă������ɍ����_�u���X�Ɉꏏ�ɃG���g���[�������Ƃ�����B���̑��A�D���ɂQ���������A�x�X�g�W�����q�����R���ŁA�ɂ������t���Z�b�g�̖������Ă��܂����B�ł������v���o�ł���B �@����ɂ��̈���ɁA�y���݂ȏ��q�����������������Ă����B�����A���̎q��͊y���݂��Ǝv�����B���q�̏ꍇ�A�ǂꂾ���f���Ő^�ʖڂ�����������B������ł���Ƃ����m�M���������B�������猾�����A�j�q�̎w���������̂��ŏ��q�ɓ��ꍞ��ł����B �@�����A���ɗ^����ꂽ���Ԃ͗]��ɂ��Z�������B���̎q�炪�Q�N�ɂȂ�̂�҂����Ɏ��͓]���邱�ƂɂȂ������炾�B���̊��Ғʂ�A�ޏ���͗��N�̐V�l��Ō��x�X�g�W�ɐi�o�����ƕ������B�����A�����c�����Ă�����A�������܂ōs���Ă����Ƒz�����邱�Ƃ͋����Ă��炢�����B �@�]������Z�̂g���ł͑싅������]�����A�����Ȃ������B���̊�]���Ȃ��������ɂ͗��R���������B���̕��͂r���Ƃ͈Ⴂ�A�n�a�̈�l���ō����茠��������ȕ��ł��������炾�B��N��ʂ��Ė~�Ɛ����ȊO�ɂ͗��K�x�݂��Ȃ��A�ږ�̍S�����Ԃ͐q�킶��Ȃ������B�i���̂������茠�͂Ȃ��̂��j �@���̍�����s�������i�[�Ƃ��Ẵg���[�j���O���{�i�����A�o�R�ɂ����L���͂��߂Ă���A�������ɋx�������ׂĒD����̂͑ς����Ȃ������B�ږ�͍ŏ����㕔�A���̌�R�x�������C���邱�ƂɂȂ����B�u���C�ږ�v�͎R�x�������ɂ������Ă̌��������Ƃ��Ă�ނ�����������ꂽ�̂ŁA�{�ӂł͂Ȃ������B �@�Ƃ��낪�A����Ȏ����܂����Ă��Ǘ��E�̉A�d�ő싅���Ƀn������H�ڂɂȂ����B������]�͂��Ɂu���㕔�̌��C���͂����Ăق����B�v�Ə�������A���x�͑싅���Ƃ̌��C�ɂ�����ꂽ�̂��B�����̐��E�́u�m�[�v�ƌ�����z�������ł���B�����O���̕����������̌ږ�Ɏ��܂��āA�������ƊǗ��E�����̕��ɐ�O���Ă���l�����邩�Ǝv���A���̂悤�ɉ^�����Q�A�������Q�����C�������邨�l�D��������B �@�����Ă݂āA��͂�\�ʂ�̐����̎����Ǝv�����B�����̃����o�[����ږ�ł͌��߂��Ȃ��B�����炪�������I�[�_�[�\���ϋq�Ȃ̂n�a�Ɂu���{�v����A�e�͂Ȃ���������������̂��B������}�l�[�W���[�Ƒ��k���Č��߂����K�������n�a�̈ӌ��ŃL�����Z����������B�u����Ȏア����Ǝ������Ă��Ӗ����Ȃ��B�v�ƁE�E�E �@���ǁA�Ǘ��E���ǐS�I�Ȑl�ɕς�������Ƃ������ĂP�N�ł������ƂƂȂ������A�����싅���Ƃ͌����Ă��A���ς��Εi�ς��A��̌��������Ƃł������B�����A�������N�x�͌ږ�����߂�Ƃ������Ƃ��m�肵���t�x�݂ɁA�P�H�ł�������h�͖ʔ��������B�����`�[���ʃ��[�O��ɉ�����Ăn�a�╔���Ɛe����[�߂邱�Ƃ��ł����B��͂蕔���Ƃ̌𗬂̊�{�̓��P�b�g�Ȃ̂������B �@���̌�A�v���C�x�[�g�ł����P�b�g�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A���͗{��w�Z�ɓ]�����B�����ł́A���������Ƃɐ̂̋���ے��ł������u�K�C�N���u�v�������c���Ă���A�u�싅�N���u���������H�v�ƒ�Ă�����ӊO�ɂ���������F�߂��Ă��܂����B�{��w�Z�̎q���B�ɑ싅��������@��Ɍb�܂ꂽ�̂������B�������ɂ����Ƃ͌����Ȃ��ނ炾���A�w������Ŋm���ɏ�B���Ă������ƂɁA���炽�߂Ėڂ��J�������v���������B �@�����r��U��ăh���C�u��ł��Ƃ��A����]�T�[�u�Ǝ߉�]�T�[�u�A�����O�T�[�u�A�i�b�N���T�[�u���g�������邱�Ƃ��Ȃ�����ǁA���̊Ԃɂ��F�ɕς�����싅��̏�ŁA�I�����W�F�ɕς�����s���|�������A��������]���E���ĉ^��ł���B �@���ʓI�Ɍ����Ă����Ƃ͌����Ȃ����A�싅�Ƃ����X�|�[�c�ɏo��A�s������ʂ��ē���ꂽ�l�Ƃ̌𗬁B����͂��ꂩ������̐l���ɂ�����҂�̎h���Ƃ�����҂�̈��炬��^���Ă����ł��낤�B�i���j �@ |
| �G���� |
| ���j���[�� |
| |