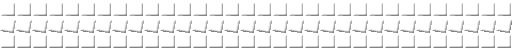 |
| Faction Novel The Univ 後編 |
| (10)不毛地帯 去る者は日々に疎し、とはよく言ったもので、ひと月もすると誰も湯口のことは話さなくなった。単位取得のかかった後期試験も迫ってきていた。理学部は、他学部に較べて卒業規定は甘い。留年の制度はなく、必修単位も少ない。だが、語学と体育実技だけは落とす訳にはいかない。ある先輩は、大学院試験に合格したにもかかわらず、教養部時代に取り残した語学の単位が取れず、大学院の入学資格を失った。翌年再チャレンジして何とか大学院には進めたが・・・ だが、守はそんな噂話を単なる笑い話として聞き流していた。まさか自分が語学を落とすなんて・・・ しかしよくよく振り返ってみると、出席率もあまりよくない。日頃の予習や復習など皆無だ。だが、前期試験はほとんど一夜漬けで受験して何とかなったし、後期も大丈夫だろう。そうタカをくくっていた。 ところが、試験まであと1、2週間となった頃、全共闘派およびそのシンパ達は、「学費値上げ反対」等を旗印に、「代議員大会」を召集した。これは各クラスから5名ずつの代議員によって構成される教養部自治会の最高決議機関である。だが、自治会執行部は紛争以来選挙が成立せず存在していない。要するに、特定のセクトが何らかの政治スローガンをかかげて人を集めさえすれば、それが「決議」ということになってしまうのだった。そして、この「代大」の結果、教養部は「無期限バリケードストライキ」に突入してしまった。 要するに、名目は何でもよいのだ。「試験を受けたくない」という一般学生の弱味につけこんで、バリストをやれば、自分達の主張が大多数の学生に支持されたと言う実績ができる。だが、一年中お休みみたいな学生にとっては大歓迎のバリストも、早く試験を済ませて春休みを満喫したい普通の学生にとっては迷惑この上なかった。 もちろん、学費値上げには守も反対である。国立大学の授業料は年間3万6千円、これは私学の約1/10で、随分親孝行していると思っている。これを「国公立・私学の格差是正」という名目で数年間で約4倍にしようという計画は、簡単に許していいとは思っていない。(ただ、文部省も考えたもので、現在在学中の学生については入学時の授業料のまま据え置きにして、新年度の入学生から上げようと言うのだ。)けれどもバリケードストライキという戦術は、大学のキャンパスから学生を遠ざけるだけで、反対運動として有効とは思えない。事実、バリスト決行以降、大学は閑散としてしまった。学生はその間、遊んでいるのか勉強しているのかわからないが、守はこんな中途半端な時間は過ごしたくなかった。だが、いくら歯がみしていてもどうしようもない。 バリストは延々と続き、いつ果てるとも知れなかった。意志の強い人間ならこの間にしっかり勉強するのに違いないが、守は普通の学生だった。後期試験の勉強はスト解除が決まってからでいいだろう、と遊びにこそ行かなかったが、読書以上のことはしなかった。 そのうち、大学入試の時期になってしまった。入学試験の間だけはストを一時解除するという裏取引きが大学当局との間にはできていたようで、入試は静穏のうちに行われた。下級生・・・どのような人たちが入ってくるのか、守は半ば無関心ながらもちょっぴり期待するものがあった。 だが、バリストはとんでもない結末を迎えた。時間的制約のため事務手続きが間に合わないということで、後期試験は実施せず、前期試験の成績だけで単位認定を決定することになったのだ。教務係で成績表を受け取って守は愕然とした。何と第2外国語のフランス語の欄が空白となっていたのだ。すなわち不認定ということだ。不認定のリミットは越えていなかったとはいえ、あまり出席率がよくなく、予習もやらなかった守は恐らく教官にいい印象は与えていなかった。前期試験のできもあまりよくなく、「総合評価」で落とされたのであろう。いくら後期試験は頑張るつもりだったとはいえ、バリストのせいにするわけにもいかない。生まれて初めて「不合格」の烙印を押されて、守は呆然とした。だが、ぬるま湯的生活にひたりきっていた自分に、これもまたいい薬かも知れない、と考えることにした。落とした単位は2回生のうちに拾い直さねばなるまい。 大学入試の発表が行われる頃、守は実家に戻っていた。ある朝、新聞を見ていた父が、ちょっと来いと呼ぶ。何事かと思って父の指さす新聞を覗き込むと、K大学医学部の合格者欄に、森山陽平という名前がある。森山は他でもない、守の親友で、守と同期で、K大学の工学部に入学した男だ。何と、彼はバリストの休みを利用して再度受験勉強し、医学部に入り直したらしい。そう言えば先日下宿に遊びに行こうと電話したとき、「今忙しいから。」と断られたのを思いだした。 父は守に「お前は出し抜かれたのだ。」と言った。明らかに理学部は医学部より下、と決めつける口調だった。もっとも、守は医学部志望だったこともある。医者になりたいのではなく、将来基礎医学的研究をしたいというのが夢だからだ。だが、父の「絶対に浪人は許さない。」という言葉と、理学部からでも基礎医学方面には進める、という情報を得て、安全策をとったのだ。いわば自分で息子の進路を限定しておいて、今更出し抜かれた云々もないものだ。と守は反発したいのを胸の奥でこらえた。 何となく2回生の生活が始まった。昨年までと違うのは、事務手続き等でバタバタ慌てることがなくなったくらいか。自然科学ゼミナールの事務局では、上級生が学部に上がったため、自然と事務局長的役割をこなすようになっていた。事務局の仲間にも気心の知れたメンバーが揃った。これからは楽しく充実した活動ができそうだった。自科ゼミは、例年理学部新入生の半数近くを組織していた。(もっとも最後まで続くのはその半数くらいだろうが・・・)今年もPRに奮闘した結果、10個弱のゼミが結成され、各ゼミからの連絡員が選出された。最初の事務局会議に集まったそのメンバーを眺めたとき、その中の紅一点、渡部蓉子に嫌でも目が行ってしまったのは女性不毛地帯に生息している守からすれば、当然すぎるくらい当然のことだったろう。彼女は今春の新入生の一人、静岡県出身だと自己紹介で話した。静岡県、と聞いて、守は合ハイのときに出会ったN女子大の娘をふと思いだした。彼女もたしか・・・ (11)蓉子 渡部蓉子は、それまで守が自分の大学の女子学生に対して抱いていたイメージをがらっと変える女性だった。どの女子学生も彼女らなりにおしゃれはしているのだろうけれど、それがぴったり似合っているケースは少ないように守には思えた。その当時の流行と言えば、フリルのいっぱいついたアルプスの少女ハイジ風のロングスカートに、厚いコルクのサンダル。どう見ても可愛い娘ぶりっこスタイルなのだが、それが不自然に見えないのは、蓉子が小柄で目がくりっとして長いきれいな髪をもっているせいだろうか。蓉子と同じクラスの、口の悪い後輩は、「うちん大学じゃからあげんモテるんで、他の大学じゃったら普通の女学生じゃ。」と広島弁丸出しで言うのだが、仮にそうであるとしても、身近にいる女性の評価は常に相対評価であるのは世の常であり、砂漠のような不毛地帯のわが大学・学部にあっては、たとえサボテンのような女性であっても、ヨーカンのような味がするというものである。 自科ゼミ事務局活動の第1基本型は、各ゼミの行われる第5限、すなわち午後4時10分からの時間帯に教養部のゼミボックス(何とゼミナール専用のプレハブ小教室である!)を回って、啓蒙・宣伝活動をすることである。もちろん、守は蓉子の所属する「遺伝子の分子生物学」ゼミナールには率先して出かけた。彼女の顔をそこに見いだすだけで心が和むような気がした。そして、もし守にチャンスが生ずるとすれば、年に何回かの「機関誌編集」期である。すなわち彼女はゼミの連絡員なので、その活動報告は彼女に書いてもらわねばならない。ついでに印刷・製本も手伝ってもらう段取りになれば、じっくりお話しする機会もあるに違いない・・・ 連絡員と言っても、律儀な者ばかりではなく、いくら声をかけてもなしのつぶての場合だってあるのだが、彼女はその都度よく顔を出してくれた。だが、なかなか二人きりのチャンスなんてつかめるものではなかった。他の事務局員もいれば連絡員もいる。考えてみたら、彼らもまた蓉子が目当てで集まってきているのかも知れないのである。守もそれとなく気を惹こうと、ドリンクやお菓子などを買ってきてはサービスしたりもしていたのだが、それらはいつの間にか他の連中の胃袋の中に消えるばかりで、彼女のハートにはヒットしそうもなかった。 そうこうするうちに2回目の夏合宿の時期が近づいてきた。この合宿は連絡員を経てすべてのゼミ参加者に呼びかけるのだが、お世辞にも参加率は高いとは言えなかった。現事務局のメンバー以外に、2〜3名おまけがつけばいい方である。 守は蓉子にも声をかけてみた。彼女は少し心を動かしたようであった。 「行きたいんですけどー、授業休むのは困るんです。」 自科ゼミの合宿は7月の第1週、すなわち最後の講義サイクルにあたる。第2週からにすればもちろん講義を休む必要はないのだけれど、そうなると全学の有象無象の学生が大挙押しかけてきて芋の子を洗うような大混雑になる。ゆっくり釣りをしたり泳いだりボートに乗ったり、学習会なんてとんでもない雰囲気になることは間違いない。7月第1週と言えばまだ梅雨も明けていない時期だが、サマーハウスを広々と使うには絶好の時期なのだった。それに、最後の週は、教官の方も休みたいと見えて、休講もかなり多いのである。 期待していただけに、蓉子の来ない合宿は味気ないものだった。もっとも、女っ気が0だったかというと、去年の法学部ビキニ姐ちゃん達よりもずっとにぎやかだったのである。ただし、その大半は体育会系の女たらしが連れ込んだK女子大のギャル(注;当時はこの用語は用いられなかった)がほとんどで、ただ単に欲求不満を募らされるだけの存在だった。その反動かも知れないが、守たちは結構派手に盛り上がって騒ぎまくった。夜にみんなで浜へ繰り出し、メンバーの一人が弾くギターに合わせて海に向かって吠えまくった。その歌は白々と夜が明けてくるまで続いた。もっとも、昼は海水浴にも行かずに寝ていたが・・・ 後輩からの情報では、蓉子には決まった彼氏がどうやらできたらしい。同じクラスの男らしいが、今更悔しがっても慌ててもどうにもならないことははっきりしていた。「去るものは追わず。」と心の中でうそぶく守だったが、目標を失くした空虚感は否定することができなかった。 思いがけない蓉子との再接近は、次の春にやってきた。蓉子が突然事務局の活動場所である理学部の学生控室に、やってきてこう言ったのである。 「あのー、わたし今年から事務局のお仕事手伝わせてほしいんですけど・・・」守は一瞬その言葉を疑った。はっきり言っておもしろい仕事ではない。事務局員なんてゼミにとっては黒子のような存在で、下手をしたら邪魔者扱いされかねない。機関誌発行と言えば聞こえはいいが、ボールペン原紙に書いたなぐり書きの原稿を、一枚一枚謄写版で擦って袋折りにし、堂々めぐりでホッチキス留め。そんなことを少人数の徹夜でやっているのだ。それを彼女も知っているはずなのに・・・守の脳裏にある期待感が芽生えた。(ひょっとして、彼女は僕に・・・) これは確かにチャンスだったのかも知れない。だが、悲しいことに守はそのチャンスを活かす術を知らなかった。男女交際なんてとんでもないという家庭教育を受けて育った守。未だに父親は、「女なんかできたら勘当」という言葉を口にする。それに強い反発を感じながらも、女性とはどうやってつきあったらよいか、頭ではわかっているつもりでいても、金縛りにあったように行動に移せない。 蓉子はそれから事務局に顔をだすようになった。実質事務局長としてとりしきっている守は、とにかく彼女に仕事をしてもらわなくては、と思ったが、彼女を目の前にすると、どうしても意識過剰になってしまい、仕事が頼みづらく感じるようになった。去年は割合気軽に何でも頼めていたのに・・・ 機関誌の編集作業が遅くなったある日、たまたま他の事務局員達がバイトなどで出払い、二人きりになったことがあった。彼女は机の隅っこで黙々と仕事をしてくれている。守はインスタントコーヒーを入れ、大学生協の売店から買ってきた菓子を彼女にすすめた。彼女は黙ってうなずくだけで、口数も少ない。 そういえば前から気になっていることがあった。蓉子は人前では決して飲食物を口にしないのである。少なくとも守の前ではそうであった。ダイエットでもしているのか、単なる嗜好の問題か、あるいはそういう厳格な「しつけ」を受けて育ったのか・・・ そのことがこの場の雰囲気をますます緊張させているようで、守は逃げ出したくなるような気持ちにとらわれた。 やがて夜も更けたので、彼女を下宿まで送っていくことにした。うまいことに、守の下宿と、彼女の下宿する何とかマンション(家賃は倍)はすぐ近くであった。守は自転車なので、彼女とは自転車をはさんで並んで歩くことになった。何気ない世間話をもちかけようとするが、どうしても沈黙の時間が長くなってしまう。彼女のマンション前で別れるとき、突然彼女は謎めいたことを言って身を翻した。 「誰か一緒に住んでくれないかなー。」 守と蓉子との接触はそれが最後であった。 (12)図書館 大学の図書館は教育学部の向かい、本部西門の脇にある。教養部にも図書館はあるのだが、守がもっぱらこちらによく来るのは、建物が新しくて味気ない教養部より、こちらの方が壁に蔦がからまったりして多少ともロマンチックな雰囲気があるからだ。もっとも守は図書をせっせと借りる習慣はない。読書傾向は多読でも精読でもなく、気に入った本を速読かつ重読する方である。とことん気に入った本は、自分の本棚にないと気が済まない。だから古本屋巡りに精を出すことが多いが、古本だからといって大して割引きしないのが京都の古本屋の悪どいところである。新品にしようか、古本にしようか迷うぐらいのところに価格設定がしてある。値上がりする前の版に、表示価格を上回る価格をつけているのはザラ、そのくせ買い取りのときは問答無用で買い叩かれる。一番賢いのは先輩から安く譲り受けることだが・・・ 守が図書館で時間を消費するのは、もっぱら実験などのレポート書きである。学問的意義のはっきりしない講義などはとっくに御免こうむっている守にとって、実験の時間というのは、最も充実した時間の過ごせる授業である。守が、教養部で最も面白かった授業は何か?と聴かれたら、迷わず「物理実験」と答えるだろう。実験書に書いてあることをただ黙々とこなしていくだけの化学実験や、はっっきりした結果の出ないことが多い生物実験より、いろいろ工夫の余地があって、うまく行けばきれいな結果が得られる物理実験は、特に充実感がある。 その日も守は実験のデータ処理をやっていた。実験レポートは、やってすぐまとめにとりかからないと、どうせ提出期限は1週間後だからと後回しにすると、締切が過ぎてからあっ!ということになる。書き上げたらすぐその足で実験室前の提出箱へ投げ込みに行くのも、習慣化していた。 「鈴原くーん」と、女性の声。この大学の中で、守の名前を呼んでくれる女性はおそらく片手で十分だろうが、顔を向けると岡田美穂子が立っている。美穂子は、1年のときの白浜合宿で知り合った法学部の女子学生のうち、背の高い方である。あのとき以来、学内ですれちがったときには会釈を交わすようになった。その美穂子が今日は何の用だろうか。 「ちょっとレポートのまとめ方がわからへんし、手伝うてくれへん?」 何のレポートかと尋ねると、「自然科学概論」だという。文科系の学生であっても、教養部の間は、自然科学の単位をいくつか取らねばならない。もちろん、理科系の学生にも人文・社会科学の単位が要求される。テーマは何かと見せてもらうと、「産業革命前後における科学方法論の違いについて」などとある。 「鈴原さんって、自然科学ゼミナールでしょ? こういうん、くわしいんやないかと思て。」 痛いところを突かれた。実は科学史については本格的に勉強したことはない。けれど、自科ゼミ傘下に「自然科学史」ゼミというのがあり、そこが、バナールの「歴史における科学」のテキストを使っていたはずだ。ここはそれに頼るしかない・・・ 「ちょっと待ってて。」と美穂子に言い残し、守は書庫へ向かった。「歴史における科学」の背表紙はすぐ見つかった。だが・・・5巻あるはずの本は全部揃っていない。貸し出されたか、それとも盗まれたか(大学紛争以後これが多いのだ)は分からないが、めくってみると、案の上産業革命のところが抜けている。仕方がないのでそれらしいテーマを扱った他の本を探してみる。表紙のとれかけた戦前ものの古書のなかにどうやらそれらしきものが一冊見つかった。(これで辛抱してもらおう。でも、むこうから話しかけてくるなんて、これはひょっとしてラッキー、かな?) レポートの件はすぐけりがついたが、二人はしばし雑談に興じていた。(不思議だ。)と守は思った。渡部蓉子のときは、あれだけガチガチに緊張していた自分が、この美穂子とはどうして気楽に話ができるのだろう。蓉子と美穂子との違いと言えば、まず背の高さ、関東弁と関西弁が頭に浮かぶ。だが、それだけではない何か決定的な違いが他にあるようだ。蓉子はいかにも女、女していた。女性としての強みと弱みが同居していた。だが、この美穂子はあまり女を感じさせない。もっとも、守には白浜でのビキニ姿がまだ目に灼きついているが、ここでいう女らしさというのは、多分に性格的なものだ。 「異性との間に友情は成り立つか?」という古典的テーマを守は思いだした。 男女平等が勃興しつつあるある世の中だもの、友達としてつきあえる女性がいたって構わない、と守は考えた。美穂子とはそれができそうな気がした。美穂子は弁護士志望だと言う。言葉の端々に女権意識が漂っている。弁舌も立ちそうで、下手なことを言うとぶっ飛ばされそうな雰囲気がある。特に美人とは言えないが、他学部の馬の骨に過ぎない自分に多少とも関心を持ってくれたことは嬉しかった。 法学部もこの図書館のすぐ近くであることも意識下にあったのだろう、守の図書館通いは頻度を増した。昼食も、美穂子のよく現れる大学生協の中央食堂を利用するようになった。彼女は同性の友人と一緒に現れることが多く、話しかけるチャンスは多いとは言えなかったが、守はとりあえず「顔つなぎ」のつもりだった。理学部の女性達は「恐れ多い」方ばかりであったし・・・ 2回生も終わりに近づき、守の身辺も慌ただしくなってきた。一つには、理学部の自治会が3・4回生の先輩達の努力によってついに「民主化」されたことである。選挙で全共闘系の「S闘」候補に接戦の末の勝利であった。一旦民主化された以上は、来年は自分達が守らねばならないことになる。その礎を築くためには、「自主ガイダンス」運動を成功させねばならない。「自主ガイダンス」とは、 理学部進級にあたって、各講座や研究室の内容を調べあげて冊子にまとめ、専門科目履修や所属系決定の助けにしようというものである。学科制というものが存在せず、広く学ぶことはできても、専門意識を養成しにくい弱点を補う意味がある。守も実行委員の一員として、研究室巡りに精を出していた。 そんな中、教養部の最後の後期試験もまたバリケードストライキ突入となった。去年のことがちらっと頭をかすめる守だったが・・・ (13)重箱の隅 2回生の後期試験は、またもやバリケードストライキに突入した。これで教養部で4回ある試験のうち、3回はバリストで潰されたことになる。今度は試験実施不能という事態にはいたらなかったものの、またしても守はミスをおかしてしまう。1回生のときに落としたフランス語の単位は、2回生の分も含めて首尾よく取れたものの、何と英語の単位を一つ落としてしまったのだ。それは、たまたま守がサボっていた最後の講義で、「どうせ今度の試験もストでできないだろう。」と、担当教官が「レポート課題」に切り替えていたのだ。守がそのことを知ったときには、既にレポートの提出期限は過ぎており、教官に直接電話をかけて泣きついてみたが、剣もほろろに拒否された。自業自得とはいえ、高校時代からの得意教科で、金城湯池ともいうべき英語を落としたのは、守にとって屈辱的だった。かくして、守は学部進学後も週に一度は教養部の門をくぐらねばならない羽目になったのである。 学部進学は、守にとってはさして画期的な節目とは言えなかった。教養部の頃から学部にいる時間の方が長かったのだから・・・学部における講義は、必修科目は何もなく、自分で必要と思うものだけ取ればいい。ただ、学部の先生方の講義は、教養部の先生方のそれに輪をかけたように単調かつ無味乾燥なものが多く、守の知的好奇心を刺激するものは数えるほど、いや数える必要がないほどだった。これでは自分の専門分野は、結局独学するに如かず、という結論になるのである。 だが、カリキュラムに専門的な実験・実習が加わったことは、魅力的なことだった。3回生では、専門分野を固定せず、いろいろな研究内容・研究方法を体験させるように計画が組まれており、その中から自分に適したものをじっくり選ぶことができる。長期休暇を利用して野外実習が組まれているのも楽しみだった。 守はその中でも、将来志向する分子生物学方面の実習を重点的にとった。確かに、電子顕微鏡をはじめ最新の機器を駆使して行う実験は面白かった。だが、いろいろな研究内容を体験すればするほど、「自分のやりたいもの」がぼやけていくジレンマを守は感じるようになった。ある分野を突き詰めていけばいくほど、その分野における独自性を求めれば求めるほど、研究テーマは重箱の隅をほじくるようになり、辛気くささ・泥くささばかりが鼻につくようになってくる。そこには理学部で生物学を志す者なら誰でも一度は憧れる「日本人最初のノーベル生理・医学賞の片鱗すら窺うことはできない。 分子生物学は未だ実用にはほど遠い段階である。研究に取り組んでいる企業は数えるほどしかない。大学院に進むための競争は酷しいのにもかかわらず、5年を費やして博士号を取得しても、就職できるポストがない。すなわち、OD(オーバードクター)が大量に発生している。齢が30に近くなっても、アルバイトで生計を立てながら研究室に残らねばならない。そんな先輩達の状況を見るにつけ、将来への不安がよぎる守だった。 自然科学ゼミナールの方は、「引退」するわけにはいかなかった。有能な後進が育っていなかったのだ。守が手腕を発揮すればするほど、後輩達はそれに頼ってしまうという悪循環が生じつつあった。さらに、守には理学部自治会の仕事が加わった。当時の学生部長は、反自治会、というより反民主団体意識の固まりのような、数学のN教授であり、執行部はことごとく彼の嫌がらせに手を焼かねばならなかった。赤ヘルメットの連中のように暴力的吊るし上げやバリケードストライキという戦術は使えない。きりきりと歯がみするようなことがよくあった。いくら学問的には世界に名を知られた学者であっても、社会常識的には赤ん坊同然の人間もいるのだということを思い知らされた。 一方、守のプライベートにはさしたる変化はなかった。理学部の女子学生とはほとんどコンタクトはない。岡田美穂子とは、たまたま会ったときに話を交わす程度。積極的につき合おうにも、彼女の電話番号すら知らない。今更改めてそれを尋ねる勇気はない。 理学部には、長年K女子大と合同でやっているフォークサークル「信天翁(あほうどり)」というのがある。毎日、放課後になるとK女子大生たちがギターを抱えてやってくる。信天翁は植物学教室の学生控室を活動場所にしているようだが、その楽しそうな様子を見るにつけ、欲求不満の募る守だった。まったく、彼女らは別世界から来た天女のようだ。世の中にはこんなに可愛い生き物も生息しているのだ。守もフォークソングは嫌いではないが、ギターも弾けず、その輪の中には加われそうもなかった。このままだと自分は研究室の片隅でうず高い埃に埋まってしまいそうだ。かつてそれを望んで理学部を選んだはずの守が、今や相反する感情に支配されていた。人間とは矛盾に満ちた生き物である。 そうこうするうちに、京都へ来て3度目の夏が来た。8月が近づくと、どこでも原水爆禁止運動が活発になる。理学部自治会でもカンパを集めて広島に代表を派遣しようということになった。大学周辺の地域を回ってのカンパ集めを、近くのK芸術大学の自治会と合同でやろうという話が持ち上がった。向こうの自治会執行部はほとんど女性だそうである。その日、くじ引きで一緒に周るカップルを決め、守のパートナーに決まったのは、何と向こうの自治会委員長だった。彼女はすらっと背が高く、少しちぢれたショートヘアーの娘である。第一印象、話やすい娘だと思った。その勘は当たった。 (14)下町娘 吉川かおり(香?)と彼女は名乗った。自治会委員長と言うから1つ年上の4回生かと思っていたら、3回生とのことだった。そのことは守にほのかな希望を与えた。署名用紙とカンパ袋を持って二人は歩き出した。 「背高いね。何cm?」 「1m64cm。だからハイヒールははけへんの。いつもこんなペッタンコの靴はいてる。」と、彼女は茶色のナース靴風の靴を指さした。 とすると・・・自分との慎重さは11cmか、まあそれほど不釣り合いではなかろう、と守は考えながら、単にこの娘は背が高いだけでなく、すばらしく均整のとれた体つきをしていることに気付いた。美穂子も同じくらいの身長だが、この娘に比べれば幾分短足気味だ。 「何かスポーツやってた?」 「うん、高校の時陸上部で中距離やってたの?」 「うわ、それやったら一緒に走ったら負けそうやな。」 「もう今は走ってないからあかんわ。この頃は運動いうたらスケート行くぐらいやし。」 「え?スケート? こんな真夏にスケートするとこあるの?」 かおりは大阪のあるスケートリンクの名前を挙げた。どうやら大阪出身の娘らしい。実は守も一度だけ友人に誘われてスケートに行ったことがある。最初はあんな包丁の刃みたいなもので立つことすら不安だったが、その日のうちに何とかリンク中央まで出て滑れるようになった。そのときの経験を話すと、 「それやったらちょっと練習したらもっと上手になるわ。カーブとかバックとかできるようになったら面白いわよ。」 「今度一緒に行ってコーチしてくれる?」 「ええわよ、いつでも。」 知り合って5分も経つか経たないううちに、もうこんな話がすらすらできる自分が信じられなかった。他の女性なら口ごもって言えそうもないことを、彼女はいともたやすく言わせている。そういう不思議なキャラクターが彼女にはある。こんな女性に出会ったのは生まれて初めてだ。 「芸大で何やってるの?」 「何してるか、当ててみて。」 「うーん、デザインか何か?」 「は、ず、れ。私音楽専攻なんよ、専門は打楽器。」 「へえ、芸大って美術だけかと思ってた。何でまた自治会活動何かやり始めたん?」 「芸大ってね、すごい封建的なところがあるの。特に音楽はそう。教授が絶対的な権力持っていて、教授の許可がないと楽団すら組ましてもらえへんのよ。せっかく好きなことしたくて大学来てるのに、これはあかん、あれもあかん、ばっかりで。それで自治会通して文句言いに行ってたら、いつの間にか役員にされてしもたん。」 坊ちゃんの道楽みたいなところのある自分たちの自治会に比べて、彼女らは随分切実な要求を掲げて頑張っているな、と守は感じた。 「大阪のどこらへん?」と、守は彼女の住所にさぐりを入れる。 「住吉区って知ってる?」 「うん、行ったことないけど親類がいると思う。」 「うちの家、商店街で食堂やってるの。帰ったらときどき手伝わなあかんのよ。」 しめた、と守は思った。守の祖父母も長年食べ物商売をやっている。守も小さい頃からよく店の手伝いをしている。しばらくはその話題で盛り上がった。 肝心の原水禁運動をほったらかしにしておくわけにはいかない。二人は割り当て地域にやって来ると、各家の戸を叩いて、署名やカンパの訴えを始めた。さすがに京都はこういう面では革新的な土地柄と言うか、ほとんどの家が快く協力してくれる。カンパも100円や200円ではなく、千円札を出してくれたり、中には貯金箱の中身を丸ごと渡してくれる家もあった。カンパ袋はたちまち底が抜けそうに重くなってきた。もっとも、いつもこんなに調子がいいとは限らず、かおりと自分のコンビが、相手に好印象を与えているのだ、と守は解釈した。 もともと守はカンパ集めには少しばかり自信があった。初対面の人には割合好印象を持たれる方だと思っている。その上、今日はかおりという心強い味方があった。彼女は先ほどからの会話通り、気さくに誰とでも話せる才能の持ち主で、何やら渋っていたおじさんやおばさんも、彼女に言われると嫌でも財布の口を開けざるを得ないような気持ちになるようだった。 それでも、中には保守的な家もないことはなかった。 「うちは労働組合とか、学生運動とか、そないな人らとはようおつき合いしまへんのどす。」 そう大上段に来られると、何か言い返してみたくなる。 「何で学生運動があかんのですか?」 「人間社会には心言うモンが大切どす。あんたはんらは心いうもん忘れて、やれ闘争とか、ストライキとか、物ばっかり要求してはるのと違いますか?」 「平和とか、健康とか、最低限のものを要求するのは当たり前でしょう?」 「それ、そういう考え方がそもそもいかんのどす。もう帰っておくれやっしゃ。」 社会の上に立つ者の心がねじ曲がっているからこそ、国民大衆は立ち上がらざるを得ないのだ。誰が好んで喧嘩や闘争をするだろうか。守はかおりと一緒に憤慨しながら、何やら熱い共通の感情に支配されていることを感じ始めていた。 十分署名も目標数を超えたので、二人は引き揚げることにした。帰りもまた話題は尽きなかった。この娘は生粋の下町っ子だった。渡部蓉子は相当のお嬢様だった。岡田美穂子は見かけはサバサバしているが、父親は大学教授らしい。これまたハイソの匂いがした。自分にはこんな下町娘の方が合っている、と守は感じた。かおりの漂わすムードに何とも言えぬ安心感を守は感じていた。 自治会ボックスに戻ったが、予定時刻までに帰って来ているカップルはそれほど多くなかった。一番最後に戻ってきた二人は、どうやら喫茶店でダベっていたらしい。そいつは反則だ、それなら僕たちだって、と思ってもすでに遅かった。結局かおりとはそのまま別れた。また近いうちに会えるチャンスがあるだろう、何かそんな予感がしたのだが、ついにチャンスは巡って来なかった。守はたびたび岡崎にある芸大の前あたりを自転車でウロウロしては、偶然の出会いを期待したのだったが、木立に中にある古めかしい芸大の建物は、いつも守を拒絶するかのごとく、冷たく佇んでいた。 (15)自炊生活者 学部へ上がってから守は京都での下宿生活を辞めた。2つめの下宿でも家主の婆さんに何かと難癖をつけられ、いいかげん京都の人間関係が嫌になっていたのと、たまたま大阪の吹田に父の職場の関係で安いアパートが借りられたからだった。片道1時間半の通学は近いとは言えなかったが、2Kのアパートは一人暮らしには広々としていて、気楽だった。時々親父が突然泊まりに来て小言ばかり言うのは閉口だったが・・・ このアパートにはもちろん風呂もキッチンもついている。大学が休みの日には、自炊するようになった。もともと台所仕事は嫌いな方ではない。ただし、一人暮らしは何かと非能率なものだ。一度カレーライスをこしらえると、3日くらい続けてカレーだった。しまいには腸の具合がおかしくなり、出てくるものもカレーになった。料理を作るのは楽しいが、片づけるのは嫌いなので、ついつい流しが食器の山になったままのことも多い。そうするとゴキブリさんにとっては絶好の生育環境となる。殺虫剤を振り回して集団虐殺に走る守だったが、それくらいで絶滅する相手ではなかった。 半分下宿人のような、半分自宅通学者のような生活をしていると、何か思想まで変わってくるようだった。それまでは激情ばかり先行していたのに、ちょっと離れたところから評論家のような物の見方をするようになったと自分でも思う。それが進歩なのか、退化なのかは自分では判らなかったか・・・ 学部には必修科目というものは何もない。守は気に入った講義のみに顔を出し、その合間には図書館で自習することが多かった。自治会BOXにも時々顔を出すが、すると必ず何か仕事が待っていた。たいていそれは宣伝のビラ書きか、さもなくばビラまきだった。校舎に大字報を貼る仕事は、一度テラスへ出て高所恐怖で身動き取れなくなってから御免こうむることにしていた。学生控室にはうっかり足を踏み入れると、悪友どものトランプの相手をさせられる。だが、生物系の評議員として自治会に出ている守としては、「選挙対策上」、顔つなぎもしないといけないのが辛いところだった。とはいえ、生物系の連中は、S1の数学系の連中よりはるかに人間味があってつき合い易かった。 学部には普段の講義以外にも魅力的なカリキュラムが用意されていた。それは春休みや夏休みを利用して行われる「野外実習」である。3年の夏は琵琶湖での「臨湖実習」。3年から4年の春は白浜での「臨海実習」。4年の夏は木曽福島での「陸水生物実習」。生の生物に接することができるという喜びも無論大きいが、生物系の学生達にとってこれらの実習はいわば「修学旅行」のようなものであり、お互いの親睦を深める絶好の機会なのだった。とりわけ「臨海」と「陸水」は、期間も1週間くらいあり、共同生活体験ができる。 「臨海実験所」は、自科ゼミで毎年合宿に行っているサマーハウスのすぐ隣にある。夏もいいが、梅花薫る春に行くのもまたそれなりの風情があった。実習の内容はまずウニを使った発生の実験。生きたウニを採ってきて卵巣と精巣を取り出して受精させ、経時観察する。教科書に載っているままの光景が解剖顕微鏡の下で展開されるのには興奮した。もっとも学生達の最大の関心事は、実験材料の余りのウニをどうするかということにある。実験時間が終わると、学生達は奪い合うようにウニの「試食」に走る。もちろん、その対象は、雌ウニのみであり、雄は哀れにもバラされたあげくゴミ箱直行となる。 そしてスズキとモンゴウイカを使った解剖実習。材料はピンピン動いている「活けもの」である。ここでも彼らの主要な関心事は、実験後の料理法である。やっぱり刺身がいい、いや塩焼きにしようとカンカンガクガクの論議となる。 こういう遊び半分の実験を続けているものだから、最後の「プランクトン実習」では、担当教官に実験操作のずさんなのを怒られてしまった。 いよいよ実習も最終日。学生達は打ち上げのコンパで盛り上がる。いい加減酔いも廻って、最後にうわばみ的に強い奴と酒癖の悪い奴のみが生き残ってウダウダやり始めた頃、守は宿舎の縁側へぶらっと足を向けた。何人かの学生達がたむろしていて、その中に紅一点の寺谷貴子がいた。彼女とはそれまでコンタクトがなかったわけではない。自治会関係や授業等でも時々会話は交わしたことがある。どちらかといえば、あまり理系臭くない、文系的なところがあって、守とは結構話が合った。彼女には大学構内ではたいてい行動を共にしている原田敏広という彼氏がいる。原田も生物系だが、今回の合宿には参加していない。そのせいか、彼女の後ろ姿は少し寂しげである。守は今回の合宿にカメラを持ってきていたので、そこら辺にいるみんなで記念写真でも撮ろうかと考えた。声をかけてファインダーを向けると、どこの世界にも写らんと損だとばかり集まってくる人間が必ずいる。貴子にも一緒にどうぞと呼びに行くと、突然彼女は血相を変えて、 「イヤだわ、私。」とソッポを向こうとする。 「まあ、そう言わんと。いい記念になるやん。」とさらに勧めると、 「やめてよ、私写真嫌いなの。ブスだから写りたくないの。」と語気を強める。 この言葉に守はとっさに反応できなかった。貴子は目が細く、平板的な顔立ちで、学生達は陰で「平安美人」と呼んでいる。だが、それとて結構愛敬があると思っていた。スタイルはなかなかのもので、特にお尻の形は抜群だと守は思う。だが、「そんなことないよ。君ってとても魅力的な人だよ。」というようなフォローがすぐにできないのは守の性格的なもので、どうしようもない。結局、守の沈黙は暗に彼女の主張を認めたことになってしまい、彼女はますます不機嫌になってしまった。やはり何らかのフォローを期待していたのか・・・ そう言えば、少し前に思い当たる出来事があった。守は貴子の彼氏、原田敏広にふとした機会にこんなことを言われたことがあったのだ。 「彼女、君とつき合いたがってるで。」 そのとき、守は原田の言わんとしていることが理解できなかった。貴子と原田は誰もが公認の仲のはずだ。それがどうしていきなりそんなことを言い出すのか。原田は肩まで伸ばした長く美しい髪を持ち、色白の美男子である。性格もさっぱりしていて守は好きだった。そんないい彼氏を持ちながら・・・どうして? 本人を目の前にしていなかっただけに尚更不可解で、その言葉は聞き流すだけに終わったのだが・・・ その事件以来、貴子は学生控室などでもことさら守に冷たく接するようになった。守は怒るでもなく、彼女はもっと自分の魅力に自信を持てばいいのに、と思うのだった。その後彼女はいつの間にか原田とも別れ、大学院生とつきあうようになった。卒業式の日、守が最後に見たのは、その彼氏とそぞろ歩く魅力的な「お尻」だった。 (16)いちご白書 気がつくと守はもう4回生になっていた。そろそろ「出口」が気になり始めてくる。守も理学部に入学した以上、もちろん「研究者」が目標である。そして密かな憧れは「日本人最初のノーベル生理・医学賞」にある。自分の努力と才能・そして運が三拍子揃えば、それは手の届くところにあると思い込んでいた。だが、大学院や研究室の実体に近づけば近づくほど、理想と現実とのギャップがはっきり見えてくるようだった。「バイオテクノロジー」はまだ実用化には程遠く、民間就職もない。そんな中、守も他の学生達と同じく、6月の教育実習を迎えることになった。教師になりたいというより、研究者としての先行きが不安な以上、教員免許くらいは一応取っておきたい、いわば安全弁としての位置づけだった。 だが、この2週間の実習体験は、守に予想以上のインパクトを与えてしまった。母校で出会った高校生達は、自分がかつてそうであったとは思えないほど守の眼には純真に映った。彼らは、自分のつたない授業を一生懸命に聴いてくれ、プラス評価・マイナス評価を含めた正直な感想を書いてくれた。その中で、守は彼ら高校生が、自分達と年齢が近く、生活感覚の共有できる教師を待望していることをひしひしと感じた。守の母校は、戦前からの「伝統校」で、勤続20、30年のベテラン教師が大半だった。そこには競争原理ははたらかず、生徒が理解しようが理解しまいが、わが道をひたすら行く授業が当たり前だった。授業以外の面ではなおのこと遠い存在だった。守たち友人グループの間では、「授業なんか何の足しにもならない。自学自習あるのみだ。」が半ば合い言葉になっていた。だが紛争の後遺症も薄れ、時代も変わってきている。生徒達の期待に応えて、その現状を打開してやりたい、そんな義侠心のようなものがふつふつと沸き上がるのを守は感じたのである。 (いや、俺にはあくまで研究者としての道がある。最終的に教師になるにしても、大学院に行ってからでも遅くはないではないか。)守は辛うじてその線で踏みとどまった。だが、留年してでも大学院に、という執念はもうなくなり、「滑り止め」に教員採用試験も受けてみようと言う気持ちが生じてきていた。そしてその誘惑に守はついに「負けた」。すなわち7月からは、その末にある教員採用試験と、8月にある大学院入試の両方の勉強をしなくてはならなくなった。「二兎を追う者は一兎をも得ず。」という諺はよく承知していた。だが、どちらか一方に絞りきれるほど、今の守には将来への確信は持てなかったのだ。 「共倒れ」を避けるため、守は次のような学習計画を立てた。すなわち、教員採用試験の1週間前までは、大学院の方の勉強と、教採の資料収集にあてる。そして、教員採用試験の勉強は1週間の短期集中決戦で乗り切る、というものである。それで合格ラインに届くかどうか、自信はなかったが、大学院入試のことを考えると、1週間というのは割ける時間の限界だった。 苦闘の2ヶ月あまりが過ぎ、秋が来た。結果は守の内心の願望を見すかすように正直だった。大学院は二次試験で完敗した。教員採用試験は一次試験はパスし、二次の発表待ちだった。二次の感触は決して悪いものではなかった。 そんなある日、守は大学構内で岡田美穂子に声をかけられた。何か張りつめていたものが切れて力が抜けたような気分を守は感じていたところだった。どちらからともなく、お茶を飲みに行こうということになった。ひょっとすると、美穂子もまた何らかの原因で脱力状態なのかも知れないと、ふと守は思った。いつもは大学生協の「エスポワール」なのだけれど、今日は何となく学外に出たい気がして「駸々堂」にした。ここは「学生貴族」のたまり場になっている店だ。 どうやら高校教師になることになりそうだ、と守は美穂子に言った。そう、と美穂子はクールな反応だった。 「でも、研究には未練はないの?」 「未練はないと言ったら嘘になる。でも当てもなく留年して目指そうというほどのこだわりはなくなってしまった。大学院に受かった連中は、才能はともかく、執念はものすごい。あれには勝てそうもないと言う気もしてきたし・・・」 「鈴原君らしくない弱気ね。でも高校の先生だって立派な仕事だと思うわ。何とか賞目指すばかりが科学者じゃないでしょう。でもね、私、鈴原君にはもっと向いている仕事があるとずっと思ってたの。」 「それって一体何?」 「あなたが検事してて、法廷で弁護士の私と対決してる夢みたことあるわ。鈴原君って何か筋道が通ってないと納得しないようなところがあるでしょう?検事にぴったりやわ。これから司法試験目指したら?」 「これでも一応理系の人間やのに、いきなりとんでもないこと言うね。」 「あら、司法試験って法学部出ていなくても受けられるのよ。知らなかった?」 「理屈こねまわすのは嫌いやないけどね・・・司法試験の受験勉強なんて何か一日中机の前に座ってて座布団が腐りそうでぞっとするよ。六法全書なんて覚える気もしない。」 「何かそれやったら私のお尻も腐り始めてるわけ?」 美穂子は笑いだした。半分冗談話とはわかっていても、何故かむきになってしまう守だった。 そこへ、中年輩の教官らしい人物が店に入ってきて、目敏く美穂子を、見つけたと見え、二人のテーブルに近づいてきた。 「美穂子ちゃん、ご機嫌さん。誰? 彼氏?」 美穂子は、守の視線を気にしながらも、はっきりとかぶりを振った。守は一瞬冷水を浴びせかけられたような気がした。 それは確かに、守も自分の友達から、「この人、彼女?」と尋ねられたら、「いや、友達やけど・・・」と否定するだろう。だが、その中には、一抹の優越感と期待感が込められているはずだ。茶飲み友達すらいない友人達に較べれば自分はまだ恵まれているだろうと・・・そしてこれから先の発展の可能性もほんのりと匂わせながら・・・ だが、無神経な教官の一言が折角高揚し始めた守の気分を重苦しいものにしてしまった。それから後の会話は、何かとりとめのない世間話に流れてしまった。 喫茶店を出て美穂子に別れを告げ、もう学生控室に戻る気もせず、守は自転車にまたがって京都駅方面へ向かった。そう、自分は明らかに美穂子に何らかの期待感を持って接してきたことは間違いない。それは、パンドラの箱のようなもので、ひとたび開けると逃げ去ってしまいそうでずっと懐に暖めてきたのだ。美穂子は司法試験合格までは独身を貫くつもりらしい。それは、守にとっては障害かも知れないが、他の男にとってもそのはずで、むしろ安心して彼女とつき合える要素になっていた。だが、いつまでもそんな見せかけの自己満足に安住していていいのか・・・自分に可能性はあるのか・・・薄暗くなり始めた京都の街が、ぼんやりと流れていた。馴染んだこの景色も過去のものになろうとしている。もう卒業まで長くはなかった。 (17)別れうた ある日の朝、大学への出がけに守は1階の郵便受けに薄っぺらい封筒を見つけた。差出人は「兵庫県教育委員会」。「合格」の2文字が透けて見える。教員採用試験の結果通知であった。嬉しかった。その封筒をそのままカバンの中に入れ、守は大学へ向かった。友人達の前で開封して見せびらかしてやろうと思った。 吹田から乗る国鉄の車内はいつものように空いていた。嬉しい、確かに嬉しいことは嬉しい。だが、大学に合格したときのように涙が滲むほどではない。何故だろうか? やはり、これは「かけた時間」の差だと守は思った。3年間の高校生活を費やした大学合格と、1週間の受験勉強で勝ち得た合格との違いだ。汗水垂らして得た100万円と宝くじで得た100万円の違いだ。どちらを好むかは人それぞれであろうが・・・ 守が学生控室に入ると、例によって数名の悪友達がたむろしていた。「何とか教員試験に受かったで。」と封筒を開けて見せた。いつもは口の悪い連中もわがことのように喜んでくれた。ただ、たまたま来あわせた寺谷貴子だけは、「あなたが教師になるなんてゾッとするわ。」と水をさした。あの事件以来、何故か守には風当たりのきつい貴子だった。 大学を出ると、守は山村慎二の下宿に向かった。彼は数学系の学生だが、自治会執行部の仲間である。東京の下町出身で、何故か守とはよく気が合う。ここしばらく、喘息の発作が出て寝込んでいると言う話だったので、その見舞いも兼ねていた。山村の下宿は一乗寺の田んぼに囲まれた農家であった。部屋に入って声をかけると、彼はこたつにうずくまって本を読んでいた。 「どう?具合は?」 「おう、鈴原か、久しぶりじゃん。」 「どうやら俺も先生になれそうや。今日合格通知が来たんや。」 「いいなあ、俺っちは留年生活に突入間近ってとこやな。」 「やっぱり院を目指すんか?」 「いんや、もう数学は自信なくなったぜ。田隅と話して来年阪大医学部の学士入学試験一緒に受けることにした。」田隅とは同じ数学系の自治会評議員である。 「そうか、お医者さんになるんか。京子ちゃんとは相変わらず?」京子とは東京にいる山村の自慢のフィアンセである。 「京子ちゃん?京子ちゃんには振られそうや。」山村は事も無げにつぶやいたが、肩に寂しさが漂っている。(そうか、山村も生活のことを心配せねばならなくなったのか・・・)最近、守の周りではこの手の話がやたらに多い。やはり同級生の南という男も、郷里の婚約者に捨てられた。同じく坂元は、恋人に大学院に行かずに就職してくれ、と頼まれて困っている。1つ先輩の入谷氏は、薬学部の八木沼さんという女性と強引に同棲生活に突入したが、周囲からごうごうたる非難を受けている。大学院生の小嶋氏は、出身大学の後輩でもある院生の吉村さんを、同じ研究室の後輩である早川氏にさらわれて憔悴しきっている。やはり院生の加藤氏は、小学校の先生をしている女徒と結婚したが、完全に尻に敷かれてヒモ生活に陥っている。みんな恋愛をしながらも、理学部生には宿命ともいうべき経済の壁に突き当たってもがいている。守はそういう浮いた話に縁のない自分がむしろ幸福に思えた。それにしても、貧しくても自分の好きな研究に打ち込めたらそれでいい、などというセンチメンタリズムに陥っていた自分の甘さがこの頃身にしみて感じられる。周りにいっぱい誘惑のしかけられているこの時代に、仙人のような生活が貫けるはずはないのだ。修行僧の篭もる山を女人禁制にするのは、人間が誘惑に弱いことの証明ではないか。 いつの間にか大学を去る時が来た。守は卒業式には出なかった。入学式の不快感をもう一度味わいたくはなかった。連中のくだらないアジ演説など、騒音以下の存在である。ただ、卒業証書は受け取りに行かねばならない。ただの紙切れに過ぎないことは分かっているが・・・ 卒業式翌日のキャンパスはがらんとしていた。学部事務室で証書類を受け取った。ワンカップ大関が一緒についていた。その足で、1回生から顔なじみの生物物理学教室の事務室のおばさん達に最後の挨拶に行った。 「鈴原さんが大学院に残ってくれないのは残念やけど、いい先生になってね。」東谷さんという、一番よく面倒を見てくれたおばさんが言った。 そして世話になった研究室に挨拶を済ませると、もう大学には何もする事はないはずだった。だが、守はまだ大学を去る前にやり残したことがあるように感じた。この心にわだかまるものは何だろうか。守はいつしか理学部を出て、本部構内へ向かっていた。工学部を抜けて、法学部の方へ近づいていた。そう、4年前のあの日、合格発表に感極まって思わず駆け出した守は、この道を駆け抜けてあの電話BOXまで走ったのだ。4年ぶりの電話BOXには同じ匂いがしていた。守は手帳を取り出し、いつしかある電話番号を回していた。 電話には母親らしい声が出た。彼女は怪訝そうな様子を少なくとも声には漂わせず、娘に取り次いだ。 「ああ、美穂子さん。鈴原ですけど。どうしてた?」 「うん、何かちょっぴり空虚感を味わってたんよ。卒業ってこんなもんかな。」 彼女も司法浪人生活に突入したはずだ。 「別に特にとりいって、というわけやないけど・・・もう君と話すんも多分最後になるやろうと思て。」 「いややわ、ますますセンチにせんとってよ。ねえ、今からうちに遊びに来えへん?一人で来にくかったら友達も呼ぶけど。」 突然のお誘いに守はどぎまぎした。だが、守は自分が普段着の汚い格好で出てきていることに気付いた。この格好で大学教授宅にお邪魔するのは・・・ちょっと気が引けた。 「うん、せっかくやけど。駅前の喫茶店ぐらいやったらあかん?うん、そしたら4時に、最寄り駅ゆうたら?京阪の枚方公園、OK、じゃあ。」 京阪三条から守は特急に乗った。テレビ付きのパノラマカーは守には目新しかった。考えてみたら、京阪電車で大阪方面に向かうのは、これが初めてだった。車窓には見たことのない景色がどんどん後ろに流れていた。ガラスごしに梅や沈丁花の香が漂ってくるようなそんな春日和だった。中途半端だった自分の大学生活も景色と一緒にどんどん後ろに飛んで行けばいいと思った。 これからやってくる景色は、守にとって未知の新天地であるはずだ。虚飾の知識欲や名誉欲に踊らされるではなく、自分の体で自分の生活を支え、生身の人間として生きて行こう。今日がその出発点にふさわしい。その思いの一部でも愛する美穂子に伝え、自分は旅だって行こう。これから先に待っている新しい青春のまっただ中へ。電車は加速度を加えた。(完) |
| 雑文へ |
| メニューへ |