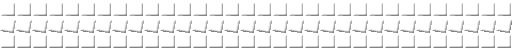 |
| 88円ライターじゃじゃモル |
| 火星大接近に寄せて |
| 2003年8月27日に火星が600年ぶりに大接近するという。かくいう小生、鈴蘭台高校時代は「地学の先生」だった。当時は素人なりに天文学にも手を伸ばし、 「天文年鑑」片手に、天体観測にいそしんだこともある。そして、1985年の「ハレー彗星襲来」を迎える。こちらは76年に1回ということで、全国的に大ブームとなった。私も同僚の先生の車に乗せてもらい、少しでも観測条件のいいところを目指して駆け回った。お天気にたたられて観測できなかったことも一度や二度ではない。 そして、この年の秋と翌年の春、私の肉眼はついに愛しきハレーの姿を焼き付けることになる。さて、その辺の顛末を当時の担任通信から、短い文章で振り返ってみることにする。 |
| 執念のハレー |
| 11月16、17日の両日、私とS先生、A先生の3名は、是非噂のハレー彗星を一目見んものと、意気込んで南紀に向かった。あいにくの曇り空。ハレー観測には絶悪の条件であったが、3名とも、それならそれで格好のレジャーだと、いささかのショックの色もなく、A先生の車は風を切って南下し、目的地の和歌山県西牟婁郡すさみ町里野部落に到着したのは、あたりもすっかり闇の午後6時過ぎであった。ここには何故か車輪のない国鉄の貨車が転がっていて、3名は首尾よくその中にもぐり込むと、インスタントの夕食のテーブルを囲んだのである。 さて問題のハレーだが、夜空を見上げると、薄曇りながら目印となる「すばる」がぼんやりと見える。これはうまく行くと雲が一時的にでもとんで、観測ができるかもとほのかな期待を抱かせたが、状況はそれ以降悪化する一方、空はたちまち星一つ見えぬ雨雲の屋根に覆われ、ポツリポツリと降り出す始末。 それでも3名は決してくじけなかった。それどころか、これで落ち着いて宴会ができると、星が見えないことを密かに喜んだ人がいたとかいないとか・・・・かくしてハレー観測会は、急遽というか予定通りというか、「麦の汁」をあおりながらの「血液型座談会」に切り替えられたのである。 その座談会の、特筆すべき研究成果を一部紹介すると・・・・血液型をバレーボールに例えると、A型「拾って拾って拾いまくるフライングレシーブ」、B型「強烈なオープン攻撃」、O型「鉄壁のブロック」、AB型「せこいフェイント時間差」 「A型の子供は、幼少の頃はわがままで愛想が悪いが、いじめられる中で処世術を身につけ、社会に出る頃にはゴマスリ名人に成長する。」 「B型の子供は、幼少時は愛想がよく素直でみんなに可愛がられるので、成長と共に増長し、わがままでマイペースな人間になる。」などなどetc・・・・ そしてついに「ハレー彗星」は、「アメー睡眠」に姿を変え、3名はついぞ最近味わったことのない快眠をむさぼったのである。 明くる日の戦果は、海釣りに行って雑魚を5、6匹ばかり引っかけただけだったが、3名はそれでも意気揚々と「もしもしピエロの現代風俗・文明における考察」という難問に取り組みながら、帰路を急いだのである。(「もしもしピエロ」が何か知りたい人はいつでも質問に来なさい。ただし女子生徒に限る。) ところが、これで我々のハレーへの執念は消滅したわけではなかった。翌18日の夜、性懲りもなく3名は、藍那の山奥へ愛しのハレー求めて3.3里、人影絶えたドライブウェーで、次々と来襲する雲の群と格闘すること2時間余、S・A両氏が探索を投げ出し車中に避難する中、決死の覚悟の鈴木隊長は、すばる(牡牛座・プレアデス星団)の南東に、かすかに星雲状にぼやーっと光るハレー彗星の姿を見出したのである。最初はどうもそれと自信なく、二度・三度と双眼鏡のレンズをこすって確認後、 「見えたぞーーーー!」と叫ぶと、車中より両氏出で来て、 「どれや、どれや。」と便乗する。 間もなく、A先生も発見。S先生は、双眼鏡がT先生所有の覗き専用ナイトデラックスであったため発見が遅れ、一人取り残されて焦るが、これまた何とか発見して歓喜の雄叫び。 とうとうその日は家に帰れなくなり、S先生宅でA型の母ちゃんから関東煮をごちそうになってから、A先生の豪邸で一泊する羽目になる。AB型の美人お母ちゃんを観賞できたのはよいが、こちらは電話でO型の母ちゃんからこっぴどく大目玉を食らい、 「怒られるのも76年に一遍やったら知れたもんや。」とうそぶく。 ハレー彗星もしもしピエロ大騒動、これにて一件落着、チョン! |
| 南海のハレー |
| それはもう、見事なサソリだった。オリオンを天球の大舞台から追い落とし、あたかもその威光を誇るが如く、南天に輝いていた。 そして、真っ赤なアンタレスに対抗するように、火星と土星が赤く輝き、長三角を形作っていた。 その荘厳な星たちに、まるで吸い付けられるように、私の足は岩場を這い、海岸線を南へ進んで行くのだった。 小高い磯から双眼鏡をサソリに向ける。懐中電灯で星図を確認する。アンタレスから数えて、6番目と7番目の恒星の間に、それは間違いなくほの白い光を発していた。右上にかすかな尾を引き、地球各地における大騒ぎなど知らぬげに、ひっそりと星野に浮かんでいた。さらに詳しくその姿を確認しようと目を凝らすと、何故かそれは視野から消え去ってしまう。一瞬凝視をゆるめると、再び視野の端に現れる。夢の中の美女のように出没が繰り返される。 今や私一人のものになったハレーに別れを告げるには未練があったが、三日三晩待ち続けた末に出会えたことに満足し、帰路についた。もう一度だけ、と南を振り向いた私に、ハレーの光芒は肉眼に飛び込んできた。さらばハレー、1986年4月5日午前4時。 |
| 雑文へ |
| メニューへ |
| |